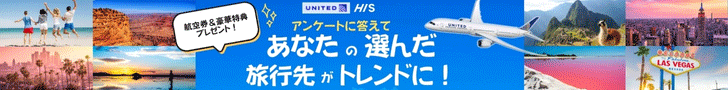ガラス工芸のさらなる可能性を求め、約10年前に日本を発ち、現在はシアトルで精力的に活動する天野芙美さん。その原動力はどこにあるのでしょうか。アーティストとして成長した今の思いを語ります。
取材・文:河野 光 写真:本人提供
 天野芙美■愛知県生まれ。2008年、愛知教育大学教育学造形文化コース卒業。2010年に富山ガラス造形研究所研究科を修了する。2013年に渡米し、2017年にはバージニア・コモンウェルス大学大学院で美術学修士を取得。以後、アメリカ各地で制作活動を行い、2018年よりシアトル在住。プラット・ファイン・アーツ・センターのガラス工房マネジャーも務める。シアトル・センターにてパブリック・アート作品「レジリエンス」が展示中(2021年12月31日まで)。www.fumiamano.com
天野芙美■愛知県生まれ。2008年、愛知教育大学教育学造形文化コース卒業。2010年に富山ガラス造形研究所研究科を修了する。2013年に渡米し、2017年にはバージニア・コモンウェルス大学大学院で美術学修士を取得。以後、アメリカ各地で制作活動を行い、2018年よりシアトル在住。プラット・ファイン・アーツ・センターのガラス工房マネジャーも務める。シアトル・センターにてパブリック・アート作品「レジリエンス」が展示中(2021年12月31日まで)。www.fumiamano.com
ガラス愛をきっかけにシアトルへ
日本でもガラス作家だった芙美さんが初めてガラスに魅了されたのは、地元の大学で美術教育を学んでいた頃。卒業後はさらにガラスの世界に没頭すべく、日本初で唯一のガラス工芸専門学校、富山ガラス造形研究所に通い始めた。最初にシアトルを訪れたのはその在学中、2009年5月のことだ。
タコマ出身のガラス作家、デイル・チフーリ氏が開校したピルチャック・グラス・スクールの短期ワークショップに参加した芙美さん。特に海外志向が強いわけではなかったが、そこで3週間にわたって指導を受けるうちに気持ちが変化していく。「シアトルにはガラス作家がたくさんいて、そうしたプロから直接、さまざまなテクニックを学べるんです。とても素晴らしい環境でした」。海外への可能性が開かれた瞬間だった。「日本のガラス工芸は、伝統工芸の側面が強く残っています。ここでは、ガラス作家も作品自体も全く違う。私もシアトルでもっと自由に制作活動をしてみたいと思うようになりました」
アメリカ留学で迎えたターニングポイント
再びシアトルに戻って来たのは、4年後の2013年6月。最初は語学学校へ通いながら、吹きガラスのアシスタントをボランティアで行っていた。アートのコミュニティーで人脈を広げることができ、居心地は良かったが、アメリカでもっと本格的にアートを学びたいという欲も出てきた。尊敬するガラス作家のジャック・ワックス氏やボヒュン・ユン氏が教えるバージニア・コモンウェルス大学芸術学部の存在を知り、奨学金も得て2014年8月に入学。ガラス以外の素材を使った作品も数多く制作した。
ちょうど30歳という節目を迎えた2015年、芙美さんは作品にパフォーマンス・アートを取り入れ始める。最初のうちは、あまりの恥ずかしさに泣いたこともあったそうだ。しかし、「伝えたい」という気持ちが次第に勝っていく。「それを乗り越えると、人目も気にならなくなりました」。大学のあるバージニア州はシアトルに比べるとアジア人が少ない。「外国人(日本人)であることを自覚せざるを得ない場面にたびたび遭遇しました。自由な表現を求めて渡ったはずのアメリカで、言葉の壁、人種・性差別という現実に直面し、伝えたいことがたくさんあるのに伝わらない、受け入れられない。そんな、もどかしい思いを、パフォーマンス・アートで表現したいと考えました」と、芙美さんは打ち明ける。

2017年には卒業制作「ボイス」が完成した。ガラスと入り組んだ木枠でできた、1辺約10フィートの箱。中は人が入れる空間になっている。芙美さんは自ら箱に入り、パフォーマンスを披露した。「ガラスを息で曇らせて、指でメッセージを書いたり落書きをしてみたり。プラカードとヘルメットで、ひとりデモも行いました」。この作品には、どのような思いが込められていたのだろうか。あまり言葉で気持ちを伝えるのが得意ではない、とはにかむ芙美さんが日本では経験してこなかったもの。それは、弱者であるかのような感覚だった。「本当はつながりたい、言いたいことがある」と、観る人に向けてメッセージを発信した。異国で抱える、どうしようもないフラストレーションをこの作品にぶつけたのだ。
パンデミックで自身も作品も変化

アイデンティティーを問う時に避けて通れないのは、自分が「女性」である、ということだった。「ボイス」完成と同年の1月、ワシントンDCで開催された女性の権利を主張する大規模デモ、「ウィメンズ・マーチ」に参加。そこでは「子宮」がアイコンとして使われていた。女性の体の一部であり、生命にとって重要な器官。にもかかわらず、社会でぞんざいな扱いを受けている。「デモ参加以降、子宮というアイデアを作品に反映させるようになりました。女性のシンボルとして、本来の力強さを形にしたかった」
シアトルのメソッド・ギャラリーで、9月25日まで展示されていた作品「ウェア・アー・ユー・フロム?」は、真っ赤なメタルパイプとロープの全長15フィートにも及ぶ「子宮」。ジャングルジムのように中に入ったり登ったりできる。「コロナ下で作品展示の機会が減り、アトリエとして使っていたシェア・スタジオをキャンセルしました。活動の幅も狭まり、自分が小さくなってしまったようで、正直かなり落ち込んでいました」と、芙美さん。そんな時、パンデミック前からの作品展示申請が受理された。「この作品を作らなくてはいけないと背中を押された気がします」。今年1月に制作をスタート。骨組みのメタル加工からロープの編み方まで多くの人の力を借り、パンデミックの逆境の中で積み上げた考えを表現した。「大好きなシアトルに戻り、本来の自分を出し切れた作品になったと思います」
誰でも手の届く街角のアートを

シアトル・センターのフィッシャー・パビリオンにてパブリック・アート作品「レジリエンス」が、12月31日(金)まで展示中だ。シアトル市による支援プログラム「パブリック・アート・ブートキャンプ」のオンライン・セミナーで学んだことを反映させた。「2020年秋から約1年間、無料でワークショップを受けられました。作品の制作費用も市が負担します。このプログラムをきっかけに、多くの人がアクセスできるパブリック・アートという分野に興味を持つようになりました」作品名のレジリエンスとは、回復する力という意味だ。「パンデミックになって、この言葉を知りました。人と直接関わることが減り、孤独を感じがちな世の中でも、それを乗り越える新しいアイデアや命が誕生する。そんな場所として、虹色の地球を作りました」今後も新しい技術を学びながら、体感を大切にした作品を世に送り出したいと話す。シアトルの街の至るところで、芙美さんのアートが見られるようになる日も近いかもしれない。