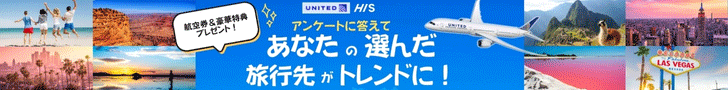みきこのシリメツ、ハタメーワク
『愛の子』を読んで
ルービン良久子さんの短編小説集『愛の子』を読んだ。
良久子さんは、小説『日々の光』の著者、村上春樹作品の翻訳で知られているジェイ・ルービン氏の奥さまでもいらっしゃる。心に響くショートストーリーが10編、ジェイ氏の英訳と共に昨年10月に出版された。
初頭の短編「愛の子」は、ハーフの子どもを持つ親はアメリカで一度くらい経験している、子どもたちの無邪気(?)な人種差別的発言が元になっている。私の息子も35年ほど前、ワシントン州都オリンピア市の幼稚園で「ケンジ、キムチ、チャイニーズ・プープー」とはやし立てられ、アジア人の多いシアトルに引っ越して来た経緯がある。「愛の子」は、その対処の仕方に素晴らしいと感嘆したのである。
その「愛の子」を読み、新婚旅行で初めて訪れた有楽町でのひと悶着を思い出した。
1981年、初夏のこと。夕方少し涼しめで、赤い革のブレザーを着ての外出。小柄な男性が「シガレット? シガレット?」と当時の夫に煙草をねだりに付いて回る。夫は「ない」と手を振りながら、やや無視して歩いて行く。と、今度は私のほうに向きを変え、同じように英語でしつこく付きまとわれた。
「うるさいわねー。『ない』って言ってんじゃないの」と、半ばうんざり放った言葉がいけなかった。私の生まれが日本橋の下町で、べらんめー調の江戸弁を聞いて育ったのが、久々に出てしまった。「なんだ、おまえ、パンパンかよぉ!」「だったらなんだってのよ!」「なにおー、このあまー!」と、飛び掛かって来そうになった時、周りの人たちが一斉にその男を止めてくれたのだ。夫は何が起こっているのかちっともわからず、少し離れて小さくなっていた。
初夏に革、しかも赤のブレザーを着て白人と歩く、というのが40年前の東京では、まだ一般化していない頃。「パンパン」、「オンリー」など進駐軍兵士相手の売春婦・妾の呼び名や「あいのこ」などが出回っていた頃だ。「勝てば官軍」の時代、「いい女(?)」を官軍の男に取られてしまう不満とは逆に、もしかしたら単純に英語をしゃべってみたかったのかもしれない、などと今なら思う。
昨年帰国して見た最近の日本、東京の光景は全く違っている。どんな時期に何を着ようが、誰も不思議がらない。あの頃とは別の国にいるような気もして、日本に不在だった年月の長さを改めて実感すると共に、酔っ払いにつっかかった若い頃を懐かしいとも思うのだ。