1944年8月、ナチス・ドイツによって占領されていたパリは、連合軍とレジスタンスの闘いによって解放を目前としていた。しかし、ヒットラーは降伏の前にパリを焦土にせよとの命令を発し、ドイツ軍のパリ市防衛司令官コルティッツ将軍(ニエル・アレストリュプ)は、ルーヴル美術館やエッフェル塔などパリの名所旧跡に爆弾を仕掛け、破壊計画を進めていた。25日早朝、そんな彼が滞在するホテルの部屋に、中立国スウェーデンの領事のラウル・ノルドリンク(アンドレ・デュソリエ)が現れ、将軍にパリ破壊をやめるよう説得を始めた。  将軍と領事、共に実在の人物だが、本作は虚構だ。実際の交渉は2週間以上にわたったようで、さまざまが提案がなされ、パリは生き残った。本作では、刻一刻と変化する状況と次第に明かされる将軍の苦渋などが描かれ、最後までスリリングな緊張感が続く。パリを救った歴史的外交交渉を描くことで、ナチス=巨悪、狂気という米国映画的な単純さからは生まれ得ない戦争・破壊回避の可能性を示す優れた戦争映画だ。原作は11年にフランスで上演され話題になったシリル・グレイの戯曲で、本作の脚本もグレイが担当。領事の説得が、少しずつ将軍の堅い防御を解いていく過程を書き込んだ脚本が素晴らしい。加えて主演の2人は舞台劇でも同じ役を演じたフランス映画界の名優。老練な将軍を演じたアレストリュプと、優雅で粘り強い領事を演じたデュソリエの名演抜きには本作の成功はあり得なかっただろう。監督はドイツ映画の傑作『ブリキの太鼓』のフォルカー・シュレンドルフ。前作の『シャトーブリアンからの手紙』もナチス占領下のパリを舞台にした作品で、ドイツ人だがフランスで育ち学んだ監督にとって、この時期の独仏関係を描くことはライフワークなのだろう。作中、領事は将軍に「もしパリを破壊したらドイツは世界の中で孤立し、フランスとの関係は永遠に修復しないだろう」と語る。戦争はいつか終わる。終わった後のことを考え、敵国に修復不能なダメージを与えるなという金言。孫子の『兵法』にも同じことが書かれている。日本は原爆投下という破壊的ダメージを経験したが、米国との関係は修復した。否、あれは修復だったのか。私たちはただ戦勝国に従属してきただけではないのだろうか。上映時間:1時間24分。シアトルは7日よりVarsity Theatreで上映中。 [新作ムービー]
将軍と領事、共に実在の人物だが、本作は虚構だ。実際の交渉は2週間以上にわたったようで、さまざまが提案がなされ、パリは生き残った。本作では、刻一刻と変化する状況と次第に明かされる将軍の苦渋などが描かれ、最後までスリリングな緊張感が続く。パリを救った歴史的外交交渉を描くことで、ナチス=巨悪、狂気という米国映画的な単純さからは生まれ得ない戦争・破壊回避の可能性を示す優れた戦争映画だ。原作は11年にフランスで上演され話題になったシリル・グレイの戯曲で、本作の脚本もグレイが担当。領事の説得が、少しずつ将軍の堅い防御を解いていく過程を書き込んだ脚本が素晴らしい。加えて主演の2人は舞台劇でも同じ役を演じたフランス映画界の名優。老練な将軍を演じたアレストリュプと、優雅で粘り強い領事を演じたデュソリエの名演抜きには本作の成功はあり得なかっただろう。監督はドイツ映画の傑作『ブリキの太鼓』のフォルカー・シュレンドルフ。前作の『シャトーブリアンからの手紙』もナチス占領下のパリを舞台にした作品で、ドイツ人だがフランスで育ち学んだ監督にとって、この時期の独仏関係を描くことはライフワークなのだろう。作中、領事は将軍に「もしパリを破壊したらドイツは世界の中で孤立し、フランスとの関係は永遠に修復しないだろう」と語る。戦争はいつか終わる。終わった後のことを考え、敵国に修復不能なダメージを与えるなという金言。孫子の『兵法』にも同じことが書かれている。日本は原爆投下という破壊的ダメージを経験したが、米国との関係は修復した。否、あれは修復だったのか。私たちはただ戦勝国に従属してきただけではないのだろうか。上映時間:1時間24分。シアトルは7日よりVarsity Theatreで上映中。 [新作ムービー]

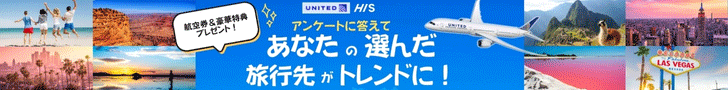











![モルモン信仰の歴史が息づく街 [ソルトレークシティー(アメリカ・ユタ州)]〜旅好きのお気に入り](https://i0.wp.com/soysource.net/wp-content/uploads/2025/03/1_1.jpg?resize=238%2C178&ssl=1)




![街中を歩くだけで心が弾む[ニューヨーク(アメリカ・ニューヨーク州)]〜旅好きのお気に入り](https://i0.wp.com/soysource.net/wp-content/uploads/2025/01/NY2.jpg?resize=238%2C178&ssl=1)


