
古い話で恐縮だが、今でも時々思い出す教訓がある。シアトル日本国総領事館に勤めていた1993年の秋、ピュージェット湾内ブレーク島で初のAPEC会議が開かれた。当時の細川護煕総理も出席し、日本政府在米他公館から応援に駆け付けた館員・職員と共に、シアトルの総領事館スタッフはシアトル・ダウンタウンのホテルに泊まり込んだ。24時間体制で日本からやって来た役人、報道陣、約200人の世話に当たるためだ。わが班は報道陣の事務室兼休憩所に配備された。
ここには臨時で雇われた地元の日系婦人もおり、普段は日本人観光客のガイドをパートでしているとのことだった。物腰が低く誰にでも平等に、丁寧に応対する、実に感じの良い人だ。彼女の仕事は「お茶出し」。丁寧にお茶を請う職員や記者ももちろんいたが、「あっ、そこのおばさん、お茶」と、乱暴に命令する若い衆も見られた。しかし、嫌な顔ひとつせず、全身からにじみ出るように優しい言葉をかけつつ対応する姿は極めて自然に感じられた。

職場での女性のお茶出しは「既成概念」のひとつだと思う。女性の仕事だと思い込んでいる日本人は、今でも存在するようだ。お茶出しをする女性は、嫌でもそうするのがサバイバルと思っているのかもしれないし、社内がうまく回るのならそれで良しとしているのかもしれない。しかし、長く続いた慣習を、問題にならないからと男女共に鵜呑みにして従うことには、自分は抵抗がある。総領事館勤務時、へそ曲がりな私は、この慣習に小さいながら抵抗する意味もあって、訪問客によく自分でお茶を入れて持って行った。中年過ぎの男がお茶を運んできたことに、訪問者は決まってびっくり、恐縮するのを私は面白がった。

女性スタッフに代わって自分がお茶を出すことにしたのは、出張でモンタナ大学を訪問した際の出来事がきっかけだ。当時のマンスフィールド・センター所長、ポール・ローレン教授(男性)が、来訪の挨拶を交わした後、そのまま一緒に台所に向かい、会話を始めながら、私たちに緑茶をいれてくれたのだ。所長、それも男性が自らお茶を用意するというのは、日本の会社や役所では考えにくいことだ。その行為ひとつで突然、その場がフラットで心地良い空間に変わり、リラックスした雰囲気になったのを覚えている。もともと日本の茶道には、このようなもてなしの精神があったのではなかったか。

お茶を出してくれるおばさんは「ただのおばさん」ではない。最近わかったのだが、APEC会議でお茶出しをしていた彼女は、何やら良家の子女という。70代に入った自分は、表面だけで、または既成概念で、人物や物事を判断したりそのまま鵜呑みにしたりせず、疑ってみることを忘れないようにと言い聞かせる。

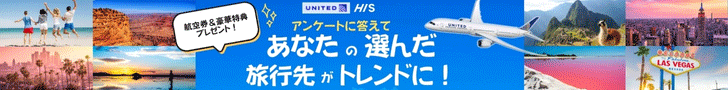














![街中を歩くだけで心が弾む[ニューヨーク(アメリカ・ニューヨーク州)]〜旅好きのお気に入り](https://i0.wp.com/soysource.net/wp-content/uploads/2025/01/NY2.jpg?resize=238%2C178&ssl=1)

![西洋の雰囲気を楽しむ[ボストン(アメリカ・マサチューセッツ州)]〜旅好きのお気に入り](https://i0.wp.com/soysource.net/wp-content/uploads/2024/11/Boston3.jpg?resize=238%2C178&ssl=1)

