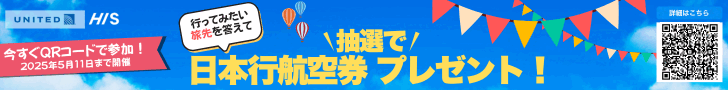73年前の1945年、広島、長崎の原爆投下により同年だけで21万人以上が亡くなりました。シアトルのグリーンレイクでは、今年も8月6日に「フロム・ヒロシマ・トゥ・ホープ(From Hiroshima to Hope)」が開催され、灯篭流しが行われました。フロム・ヒロシマ・トゥ・ホープは原爆の犠牲者、そして全ての戦争犠牲者を追悼するイベントで、平和を広く訴えることを目的としています。主催するのはどんな人たちなのでしょうか。マーサ・ブライスさん(共同設立者)、シャーリー・シマダさん(会長)、フレッド・ミラーさん(事務局長)、ボランティアで当日の司会を務めたスタン・シクマさんに話を聞きました。
※姉妹紙『北米報知』での英語インタビュー記事を一部抜粋・編集しています。
戦争への不安が高まった80年代に初開催
「同団体が発足した1984年は、戦争への不安が非常に高まっていた時期でした」。当時、日系アメリカ人市民同盟(JACL)ワシントン支局で働いていたスタン・シクマさんは振り返る。「(米ソ冷戦中で)レーガン大統領がヨーロッパに巡航ミサイルを配備しようとしていました。配備されれば一触即発。ソ連はわずか10~15分で報復攻撃ができる状況。偶発戦争につながりかねない、非常に危ない状況でした。このほかにも、中米の戦争やアパルトヘイト問題の激化など、平和と正義に関わる問題が広がっていました」。マーサ・ブライスさんも、「世界の終末まで残りわずかだとされていました。医師、看護師、そして私のような医療研究者を会員とする団体であるWPSR(Washington Physicians for Social Responsibility)は、平和と人権保護について取り組んでおり、私は当時のプログラム委員長で核問題について特に懸念していました」と続ける。

今年の灯篭流しを前にグリーンレイクにて
そんな情勢を背景に、JACLワシントン支局とWPSRとが共同で、平和を願う原爆の日イベントをビーコンヒルにあるブレイン・メソジスト教会で1984年8月6日に初開催した。基調講演をしたのはマイク・ローリー元ワシントン州知事(当時は下院議員)。第二次世界大戦中の日系人強制収容に対する補償を積極的に支援し、核軍縮問題にも取り組んでいた人物だ。最初の開催には、日系アメリカ人を中心に300人近くが集まった。
灯篭流しは当初は行われておらず、開催から数年後にマーサさんのアイデアで始まった。「ウィスコンシン州のあるコミュニティーで灯篭流しをしたと聞いて、なんて素晴らしい活動だろうと思いました。電話をかけて話を聞き、灯篭の作り方を教えてもらいました」。初めての灯篭流しは、グリーンレイクではなくワシントン大学構内にある池で行われた。「12メートルしか流れなかったんです! でも、灯篭の回収は今よりずっと簡単でした」と、スタンさんは笑う。
ワシントン大学で灯篭流しを始めた1988年には、JACLの総会議に合わせて同イベントが開催されていた。80年代は、日系人強制収容に対する補償の問題を巡ってJACLが活発に動いていた時代でもある。イベント中にレーガン大統領による補償への署名が決まったことがわかり、参加者の多くが途中退去で急きょワシントンDCに飛ぶことになったという。
文化や宗教の壁を越えて、平和への思いをひとつに
灯篭流しは広島に原爆が落とされた8月6日に行われるが、慰霊は原爆犠牲者や日本人に限定されたものではない。「原爆だけでなく、社会のあらゆるレベルにおける暴力の抑止をテーマにすべきだと当初から強く感じていました。また、さまざまなコミュニティーが関わる多文化的なイベントを目指しています」と、マーサさん。フロム・ヒロシマ・トゥ・ホープはこれまで、いろいろな民族グループや平和運動を取り込んできた。たとえば、灯篭に書き入れるメッセージは、米国書道研究会による日本語メッセージに加えて、シーク教寺院の人々によるパンジャブ語(インドとパキスタンの国境地域で使われる言語)のメッセージも加わる。2001年にアメリカ同時多発テロ事件が起こった後、特定の民族に対する暴行事件が多発し、シーク教徒の男性が射殺される惨事にまで発展した。フロム・ヒロシマ・トゥ・ホープのパートナー団体であるウィング・ルーク博物館が、シーク教徒コミュニティーと協力して追悼イベントを行った。「そこで掲げられたメッセージにとても感銘を受けたので、シーク教徒コミュニティーを誘い込んだんです。それ以来、シーク教徒の人々は灯篭流しの素晴らしいパートナーになっています」と、フレッド・ミラーさんは説明する。

(写真:Nick Turner、全面写真共に)
コロンバイン高校銃乱射事件があった1999年には、「若者による平和づくりをテーマにすべき」というフレッドさんのアイデアで、コミュニティーの子どもたちを基調講演者として招いた。若者の暴力にただ反対するのではなく、未来の平和へとつなげていく積極的な取り組みが必要だと感じたためだ。また、フレッドさんは、キリスト教の教会コミュニティーを積極的に回り、同イベントのポスターを配るようにしている。「アメリカの教会はコミュニティーが残っている貴重な場所。いろいろな形で教会との結び付きを強化しています。灯篭を水に浮かべると、宗教的なことが取り払われ、みんながひとつになれます」と、フレッドさんは話す。
戦争の悲惨さを胸に、アメリカで考えるヒロシマ、ナガサキ
シャーリー・シマダさんの母方の祖母は広島出身。原爆投下直後には、家族の安否を確認するために、手紙をやり取りしていたという。1960年に入って、シャーリーさんが広島の親族を訪ねると、祖母の甥が当時の話をしてくれた。「原爆投下の直後、彼はシャベルと手押し車を用意し、広島に徒歩で入りました。遺体をシャベルですくって手押し車に載せ、焼却炉に運ぶことを数週間続けたそうです。その時の臭いを今でも覚えていると話していました」

スタンさんの母方の親類も広島出身だ。「帰米」である母親は、戦前は広島におり、多くの友人が広島に住んでいた。ある友人は原爆投下直後、状況がわからないまま列車に乗ると途中で止まり、車掌から「この先はもう線路がないから歩いてください」と言われたそうだ。アメリカで生まれたスタンさんは、原爆投下についてどう見ているのだろうか。「原爆が一般市民に対して使われたのは、世界の歴史の中で2回あり、その責任が私たちアメリカ人にあるというのは衝撃的なことです。多くの人は原爆が昔のことだと考えていて、当時の軍の司令官が悪かったなどと言う人もいるかもしれません。でも、私が思うのは、原爆を落としたパイロットも、司令官も、政府の役人も、みんな真っ当な人たちだったのだろうということ。それでも、あの時には最悪の判断をした。私たちとそんなに違いはないんです。実行を決めたのは民主的に選出された政府。だから、私たち全員に責任があります」
一方、フレッドさんはアメリカ軍人の家系だ。「曾祖父は南北戦争時の南部連合の兵士、祖父は第一次世界大戦の兵士、父は第二次世界大戦と朝鮮戦争、ベトナム戦争で陸軍士官です。そして私は、平和運動家になりました。どういうわけか、私はいつもはみだし者になってしまうんです」。80年代に核凍結運動を進めた団体であるピース・アクションで働いていたフレッドさん。90年代に同団体の代表者としてフロム・ヒロシマ・トゥ・ホープに参加したのをきっかけに、今では同イベントに欠かせ
ないメンバーになった。「最初の参加で強く感銘を受けました。今ではもうやめられません」。ひとりひとりの思いが、灯篭流しで毎年ボランティア活動を続ける意欲の原動力となっている。
シャーリーさんとマーサさんは共に80代。現在は委員会の再編成を進めると共に、この運動を引き継いでくれる若者を探している。「先頭に立って未来につなげていってくれる人がもっと欲しい。人々の関心をかき立てられる人を探しています」と、未来へバトンをつなげている最中だ。

フロム・ヒロシマ・トゥ・ホープ
FROM HIROSHIMA TO HOPE
ウェブサイト: www.fromhiroshimatohope.org
フロム・ヒロシマ・トゥ・ホープは、広島と長崎に落とされた原爆の犠牲者、そして戦闘と暴力の全ての犠牲者を追悼することを使命とする。毎年8月6日のイベント開催では、グリーンレイク湖畔で音楽のパフォーマンス、講演、仏教僧による法要、灯篭流しなどを行い、平和、暴力によらない紛争の解決、核軍縮を訴えている。