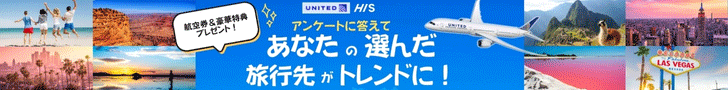がん患者だけでなく、悩める人たちの心身の健康をサポート。現在のアメリカの医療環境で今、私たちができることを探ります。
がん患者だけでなく、悩める人たちの心身の健康をサポート。現在のアメリカの医療環境で今、私たちができることを探ります。
がん患者体験記
「米国で突然がんになった」 前編
金曜日の夕方、仕事から自宅に帰る車の中で携帯電話が鳴った。病院からだった。いつにも増してひどい渋滞で、電話に出ることもできたが、やめておいた。約10分間隔で2回ほどかかってきた。金曜日の夜だし、早く話を終わらせて、医師も家に帰りたいのだろうと思い、3回目の電話は取ることにした。私の名前と生年月日を確認したあと、医師は静かに言った。
「I’m sorry. You have cancer」
予想もしていなかった告知であったけれど、意外と落ち着いて聞いていた。そして医師は、私のことをいろいろと尋ねてきた。どこに住んでいるの? 仕事は? 家族はいる? こういった患者情報はカルテ記入後、医療者間で共有される。患者もまた、どんな情報が医療者間で共有されているのかを知ることができる。
病院によるのかもしれないが、私の通う病院ではいつも予約時間ぴったりに診察が始まる。たまに待つことはあっても数十分。日本のように何時間も病院の待合室で待たされることは絶対にない。これは、医師が患者1人にかける時間が決まっており、忠実に守られているからだ。私が告知前に診察を受けた時、なかなか処置がうまくいかず、規定時間内に終わらせることができなかった。そのため、救急治療室で処置を受けるように指示された。自分で歩いて受付に行くと、すでに準備は整っており、待たされることなく個室に案内され、すぐに処置の続きが行われた。これが、アメリカの病院で待ち時間がない理由なのかと納得した。日本で同じように救急へ自分で行き、処置の続きを受けるように指示されたら、患者は怒るのだろうか。それとも、待ち時間をなくすために当たり前のこととして受け入れるのだろうか。少し、興味深い。
がん告知後は、多くのことが恐ろしいほどのスピードで決まっていく。金曜日に告知を受けて、翌週の水曜日には外科医と会い、詳しい手術の計画を聞いた。ちょうどアメリカでも新型コロナウイルス感染症が流行り出した頃。日本に住む家族を呼ぶことにはためらいがあった。というか、高齢の両親には、私ががんになったことさえ伝えることはできなかった。兄弟と話し合い、確定診断が出るまで、がんのことは両親に伏せることにした。ロサンゼルスに住む親友に相談すると、ありがたいことに仕事を休んで手術に付き添ってくれると言う。アメリカに家族がいない私にとって、彼女らの協力はとてもありがたかった。英語を話さない日本の家族と、アメリカの医師との連絡を取り持ってくれて、とても安心できた。
昼過ぎに手術が始まり、終わって目覚めた時はもう夜。翌日、執刀した外科医がベッドに来て状況を説明してくれたが、あまり良い内容ではなかった。進行が早く、予後の悪いがんであること、がんはすでに散らばっており、全部を取り切れなかったこと、あまり治療方法の選択肢がないことなど、丁寧にわかりやすく、隠さずに話してくれた。ショックを受けるというよりも、私の脳は理解することを拒否するかのように思考を停止したと言うほうが正しかったかもしれない。外科医から言われる言葉はきちんと理解していたし、今でもはっきりと覚えている。ただ、人ごとのように聞いていた。
1週間前まで、私はがんどころか病気とは無縁の生活を送ってきた。夏にはトライアスロンの競技に出たし、マラソンも走っていた。病院でのチェックアップも怠らなかった。それなのに突然、世界が変わった。当たり前のように過ごしていた日常が突然、遮断された。このまま当たり前のように年を取って、白髪やシワの増えた仲間たちといつまでも仲良く過ごせるものだと、勝手に思っていたのに。それは一瞬で崩れるのだと思い知った。(次回に続く)
 清水佐紀 ■
清水佐紀 ■FLAT・ふらっと理事。薬学学士、医学博士。東京医科歯科大学大学院にて医学博士を取得後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校AIDSインスティチュートでエイズの遺伝子治療開発の研究に従事。現在はベイ・エリアのバイオテック企業で遺伝子治療研究者として勤務。