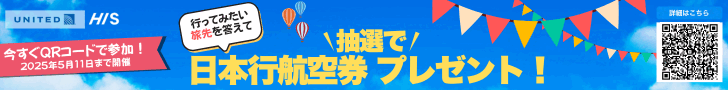パシフィック・リム疾病予防センターを創立し、27年間にわたってシアトルに住む日系人、日本人の健康調査に尽力した行方令 さん。研究者を志すまでの経緯含め、リタイア後の現在に至る道のりを振り返ります。
パシフィック・リム疾病予防センターを創立し、27年間にわたってシアトルに住む日系人、日本人の健康調査に尽力した行方令 さん。研究者を志すまでの経緯含め、リタイア後の現在に至る道のりを振り返ります。
取材・文:本田絢乃 写真:本人提供
 行方 令■大阪生まれの新潟育ち。1966年に新潟大学教育学部を卒業後、東京大学大学院健康教育学科で、中高生の双生児集団を対象に身体発育と遺伝・環境要因を研究。1971年からイリノイ大学大学院に留学し、1974年に博士号(Ph.D.)を取得。1975年より同大学公衆衛生学部の助教授として環境疫学研究を担当。1980年にシカゴからシアトルへ移り、バテル記念研究所に勤務、1983年には米国疫学学術院より上席研究フェローとして認定される。1985年、東京大学医学部保健学科疫学教室にて保健学博士を取得。1989年に財団法人パシフィック・リム疾病予防センターを創立、ディレクターに就任し、ワシントン大学公衆衛生学部にて臨床准教授も務める。2016年に引退。
行方 令■大阪生まれの新潟育ち。1966年に新潟大学教育学部を卒業後、東京大学大学院健康教育学科で、中高生の双生児集団を対象に身体発育と遺伝・環境要因を研究。1971年からイリノイ大学大学院に留学し、1974年に博士号(Ph.D.)を取得。1975年より同大学公衆衛生学部の助教授として環境疫学研究を担当。1980年にシカゴからシアトルへ移り、バテル記念研究所に勤務、1983年には米国疫学学術院より上席研究フェローとして認定される。1985年、東京大学医学部保健学科疫学教室にて保健学博士を取得。1989年に財団法人パシフィック・リム疾病予防センターを創立、ディレクターに就任し、ワシントン大学公衆衛生学部にて臨床准教授も務める。2016年に引退。




そして1971年、渡米。人生の新しいステージが始まった。最低限の生活費が支給され、授業料が免除される代わりに、学内で週 20 時間働くというのが条件。行方さんはリハビリテーション・センターでフィジカルセラピストの助手を務めることに。そこで出会ったのが、後に妻となる慶子さんだ。「家内は先天性の網膜症で目が見えず、学内のリハビリテーション・センターで盲人の新入生を助けるボランティアをしていました。1972年に全米の成績優秀な盲学生に与えられる特別賞授与式に参加するため、ホワイトハウスに招待されたこともありましたね。在学中に結婚し、博士論文の研究で IBM データカード数千枚をキーパンチするのを手伝ってもらうなど、とても助けられました」

イリノイ大学大学院で博士号(Ph.D.)を取得した後、同大学公衆衛生学部に研究助手として迎えられ、シカゴの大気汚染と呼吸器疾患の関連性を調べるプロジェクトに参加。市内の病院で毎日、ぜんそく、慢性気管支炎などの呼吸器疾患の患者数を調べ、大気汚染との関連を回帰分析していた。その1年後、助教授になった行方さんはかつての夢であった教鞭を執る夢をかなえる。当時、話題に上ることが多かった公害が及ぼす健康被害(四日市ぜんそく、イタイイタイ病、水俣病など)について講座を開講し、こんなことが二度と起きてはいけないという思いを受講生たちに託した。
シカゴの冬は寒い。よく風邪を引く幼い長女の健康が気がかりになっていた。順調にキャリアを積み重ねていた行方さんだったが、気候の温暖な土地での転職も視野に入れ始める。そんな折、シアトルのバテル記念研究所で研究科学者を募集する求人を見つけ、思わず飛び付いた。職を得て引っ越したのは、1980年のことだ。

バテル記念研究所には 12年間在籍。1983年には、これまでの功績から米国疫学学術院より上席研究フェローとして疫学者の専門職認定を受けた。その翌年、カナダのバンクーバーで開かれた、日本における大気汚染による呼吸器疾患の発症と補償金の問題について取り上げた国際疫学学会のワークショップでは議長を務め、各国の研究者たちと意見交換を行った。その結果は、バテル・プレスから出版もされている。アメリカでは、研究費の一部から研究者の給料が賄われるため、自分の研究を政府や研究財団に提案して、資金を獲得しなければならないというプレッシャーが常に付きまとう。行方さんは、数々の学会やプロジェクトに参加しながら、アカデミアの世界の厳しさも肌で感じていたと明かす。


そして1989年、在所中に自身で財団法人パシフィック・リム疾病予防センターを創立。「大きな研究所だと研究費から抜かれる管理費も莫大で、満足のいく研究が続けられないのではと心配が尽きませんでした。規模の小さい財団であれば、管理費も少なくて済みます。シアトルに住む日系人、日本人の健康調査に集中したいという希望もあり、バテル記念研究所の承諾と周囲の協力を得て財団を立ち上げることにしました」
この健康調査は、日本健康増進財団のような全国ネットワークによる健康診断をシアトルでも実現したいと考えたのが発端。日本を訪れた際、日本健康増進財団の鈴木賢二氏から全面的な協力を取り付けることに成功した。

シアトルでの健診場所も、理事のひとり、ルビー・イノウエ医師のオフィス2階を改装して使用できることになった。シアトルの日系人、日本人の健診データと、日本健康増進財団の持つデータを比較することで、当地コミュニティーの環境と健康の関連性を調査した研究の成果は、『30年にわたる日系人と日本人の健康調査研究結果のまとめ』として公式サイト(www.seanikkeihlth.com)でPDFファイルを公開している。多くの縁がつながり、シアトルの日系コミュニティーに関する貴重な研究が形となったのは、行方さんの情熱とその人柄あってこそだろう。
1992年にバテル記念研究所を退所後は、センターのディレクターとしてこれらの研究活動にまい進する傍ら、ワシントン大学公衆衛生学部にて臨床准教授も務め、再び指導者として教壇に立った。そして2016年、年齢を理由に現役を退くことを決断。引退と共に、財団法人パシフィック・リム疾病予防センターは閉鎖した。
その後もシアトル広島県人会会長を務めるなど、精力的に活動を続ける行方さん。庭の手入れや夫婦での散歩を日課とし、3人の孫の子守をしながら忙しい生活を送る。「体力維持のため、ピックルボールも始めました。かなりの量の研究資料や書籍の処分が、これからの課題ですかね」