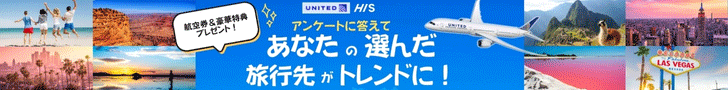金融とIT業界の最前線で活躍後、2007年に一線を退き、現在は日本の伝統文化を紹介するNPO代表を務め、師範として生け花教室も主宰する佐川明美さん。企業戦士から日本文化継承の担い手へ。しなやかに転身を遂げた明美さんが、その半生を振り返ります。
金融とIT業界の最前線で活躍後、2007年に一線を退き、現在は日本の伝統文化を紹介するNPO代表を務め、師範として生け花教室も主宰する佐川明美さん。企業戦士から日本文化継承の担い手へ。しなやかに転身を遂げた明美さんが、その半生を振り返ります。
取材・文:シュレーゲル京希伊子 写真:本人提供
佐川明美 ■ 1962年生まれ。大阪府出身。高校2年時に交換留学生として1年間、アメリカに滞在。京都大学法学部を卒業後は大和証券に入社し、1990年に企業派遣でスタンフォード大学にてMBAを取得。1991年に日本マイクロソフトに転職。日本語版Wordの初代プロダクト・マネジャーに。1994年、シアトル本社に転勤し、アジア地域のマーケティング責任者としてWindows 95のローンチに携わる。2000年、オープン・インターフェース・ノース・アメリカのCEOに就任し、2007年に同社の売却に伴い退任する。2017年にファイブセンシス財団を設立後は、日本の伝統文化の普及活動がライフワークに。ワシントン州日米協会のボードメンバーや日本企業の顧問なども務める。
旺盛な独立心で数々のチャンスをつかむ
和装が似合う、柔和な表情の明美さん。日本で女性総合職の先駆けとして金融業界をひた走り、マイクロソフト勤務、ソフトウェア開発会社のCEO就任と、IT業界の中心に身を置いた。「子どもの頃から、とにかく負けん気が強かったですね」と笑みをたたえる明美さんは、大阪で電気工事業を営む両親の元に育ち、後に弟も生まれる。母親は弟や社員の世話で手を離せず、頻繁に伯母の家、祖父母宅を行き来するうちに、自然と独立心が培われた。
こんなエピソードもある。小学1年の宿題に出た「ニワトリは飛ぶか」という問題に、母親は「飛ぶに決まってるわよ」と教える。その通り提出したが、正解は「飛ばない」。この時を境に、勉強に関して親は当てにしないと肝に銘じた。「今にして思うと、これは母の策略だったのかもしれませんね」
小学4年の時には、英語を習いたいと自分から言い出した。理由は、仲良しの友だちが英語塾に通い出したから。同じ頃、一家は大阪市内を離れて郊外へ引っ越したため、明美さんはひとり延々と電車に乗り塾に通った。6年生になると、塾は中学受験の話題でもちきりに。地元の小学校とは大違いだった。「自分も中学受験をしてみたい」とせがんだが、親も学校の教師も大反対。しかし見事、大阪教育大学附属平野中学校に合格する。
中学3年では高松宮杯(現・高円宮杯)全日本中学校英語弁論大会に出場し、大阪代表に選ばれた。全国大会の世話係をしていた大学生のほとんどが、高校留学の経験者。そこで初めて、学校単位で申し込みが必要な「AFS」(American Field Service)という交換留学プログラムの存在を知った。興味を持った明美さんは、高校進学と同時に英語担当教諭に頼み込み、プログラムの詳細を入手してもらう。そして、厳しい選考を経て、アメリカ高校留学の切符を手に入れた。ペンシルベニア州の片田舎で1年間のホームステイ。その時のホストマザーのひと言が忘れられない。それは、明美さんの人生に大きな影響を与えることになった。

ホストマザーは、ある親しいクラスメートのことを、「数学はできないけれど、頭がいいの」と形容した。明美さんは日本で進学校に通っていたこともあり、「数学ができないのに頭がいい」という図式はあり得ず、衝撃だった。「アメリカでは、人を測る物差しがひとつではないのだ。そうか、自分を測る物差しは自分で作ればいいのか」。この気付きが、留学生活最大の収穫であった。
日本に戻った明美さんは自宅から通える文系の大学で最難関、という理由で京都大学法学部を受験し、合格。やがて就職活動の時期を迎え、初めて現実の厳しさに直面した。男女雇用機会均等法が施行される1年前のことだ。優秀な女子学生の就職口は、公務員か法曹界と決まっていた。どうしても民間企業で働きたかった明美さんは、男子学生にしか届かない就職情報誌を譲ってもらい、片っ端から企業に葉書を送った。結果は、都市銀行13行を含め、軒並み門前払い。面接にも進めない、というありさまだった。

それでも、明美さんはめげない。東京に住む遠い親戚を頼り、6週間かけて就職活動に専念。ついに大和証券で初の女子総合職を勝ち取った。入社後はがむしゃらに働き、同期で常にトップの成績を争う日々。その功績が認められ、社内留学制度でスタンフォード大学ビジネススクールへの2年間の派遣が決まった。そして再び、アメリカの多様性に圧倒される。

高校時代に過ごしたペンシルベニア州は、敬虔なクリスチャンが人口の75%を占めていた。一方、スタンフォードには教会に通うカルチャーがない。まだ30代だったビル・ゲイツ氏、故スティーブ・ジョブズ氏が、カジュアルな服装で単発の講義にやって来る。「こんな若い人たちが活躍しているのか」と、ショックを受けると同時に、アメリカは自分に合っていると実感。「このカリフォルニアの青い空に、5年以内に必ず戻って来よう」と心に誓った。
帰国して大和総研に配属されたのは、29歳の頃。アナリストとして自動車業界の分析に従事するも、ビジネススクールを出たことで「問題があったら自分で解決する側にいたい」との思いを強くしていた。日本では30代での転職がまだまだ厳しい時代、チャンスは今しかない。会社を辞めたら留学費用を全額返済しなければならないが、転職をためらっていられなかった。
「会社にとって私の代わりはいくらでもいる。でも、私の人生で私の代わりは誰もいない」。会社には「温泉に行ってきます」と告げ、9日間の有給休暇を取得。「西海岸に本社のあるアメリカ企業の日本支社」に条件を絞り、東京で転職活動を行った。オファーをもらった3社のうちのひとつが、マイクロソフトの日本法人だった。東証一部上場企業から無名の会社へ。周囲の誰もが反対したが、決心は固かった。
アメリカに戻りたい一心で、
未知のIT業界に飛び込む
未知のIT業界に飛び込む

日本マイクロソフトでの仕事は、まだ発売前の日本語版Wordのマーケティング。当時の日本でワープロソフトと言えば「一太郎」が主流で、明美さん自身、Macしか使ったことがなく、WindowsどころかDOSが何かもわからなかった。社員は200名ほど。全員が中途採用で、社内の体制もあってないようなものだった。新入社員研修もなく、入ったその日から「はい、明日からこれがあなたの仕事ね」と言われ、自分でソフト一式をコンピューターに入れるところから始まった。当初は「青い目のワープロ」と揶揄された日本語版Wordは、1991年12月、無事に発売された。
次に大きな節目となったのが、同社の社運がかかるWindows 95のローンチ。日本語版の発売は英語版から早くても1年後というのが通例の中、初めて世界同時発売を目指していた。開発陣は準備万端だが、マーケティングが追い付いていない。そこで明美さんが手を挙げ、マイクロソフト本社へ2年間出向。カリフォルニアの青い空に戻るはずが、雨の街として有名なシアトルへ。そして、伴侶となるアメリカ人男性と出会い、結婚。そのまま日本へは戻らず、マイクロソフト本社に転籍した。その間、マーケティング・マネジャーとしてWindows 95のアジア地域での立ち上げを指揮し、1995年8月の英語版に続き、11月に日本語版が発売された。

その後、Internet Explorer立ち上げに携わる中、明美さんはインターネットの将来性に可能性を見い出す。Eコマース事業を始めたいと会社を辞めたが、1997年当時、日本のインターネット人口は97%が男性。通信速度は遅く、画像も載せられない。日本の女性向けに、地元ガラス作家のデイル・チフーリ氏の美しいアート作品などを売りたくても、日本からの要望は男性向けのスポーツ用品やパソコン部品などが占めていた。目論見は崩れ、マイクロソフト本社に復職するが、すでに巨大企業になっていた古巣でできることは限られている。軽い燃え尽き症候群に襲われ、再び退職を決意したのは2000年のことだ。

間もなく日本マイクロソフト時代の縁で、オープン・インターフェース・ノース・アメリカ(OINA)を設立し、CEOに就任。ワイヤレス通信技術のBluetoothをグローバル展開する会社だ。明美さんは、設立資金の調達にエンジニアの採用、トップセールスと、幅広い任務をこなした。同社のBluetooth技術は、発表前だったiPhoneにも採用された。アップル社との協議は、情報が漏れないよう、ロゴも何もない建物で行われたそうだ。投資家との軋轢や社員が辞めていくなど、つらい経験もしたが、それらを含め「短いながらも会社の設立から売却まで、会社の一生を経営者として見守ることができたのは良かった」と話す。
CEO時代のモットーは、「I assume you are great unless proven otherwise(私はあなたを優秀だと信じます。あなた自身がそうではないと証明しない限り)」だ。これは、マイクロソフトで主流だった「I assume you ignorant unless proven otherwise」という考え方の真逆を行く。マイクロソフト本社では激しい競争が奨励され、自分の成果を絶えず誇示しなければならなかった。信頼をベースにしたほうが生産性も上がるのではないか。その思いに至ったのは、ビジネススクールの影響も大きい。ライバル校のハーバード・ビジネススクールと違い、スタンフォードでは「競争ではなく協業」という考え方が浸透していた。「哲学の違いですかね」と、明美さんは語る。
2007年、OINAはアメリカの半導体メーカーであるクアルコム社への売却交渉を始めた。覚書締結から売却完了までの6カ月間、明美さんは深夜まで土日もなく働いた。心のバランスを保てたのは、趣味の生け花のおかげだ。「毎週、決まった時間に心を無にして、目の前の花に向き合いました。それがなかったら、どうなっていたかわかりません」。忙しい合間にオフィスを抜けて生け花教室に出向き、誰もいないオフィスに戻って、その花を飾る。翌朝、社員が愛でてくれるのがうれしかった。
会社の売却を見届けると、人生で初めて、目標を設定せず流れに身を任せることにした。すると、新たな出会いが待っていた。ワシントン州日米協会で知り合った人に、生け花を教えることになったのだ。「場所ならあります」、「生徒さんはこちらで集めますよ」と、とんとん拍子で話が進む。「ハイテク一辺倒だった生活から、がらりと変わりました」。大きな心境と環境の変化だった。
日本の伝統工芸に新たな息吹を


ビジネススクールで学んだ鉄則に「競争に勝つには、2通りしかない」というものがある。同じ物なら価格が安いほうが勝つ。そうでなければ差別化しかない。日本にとって、他国がまねできないものは何だろう。それは、半導体でもパソコンでもなく、日本の伝統文化なのではないか。明美さんはそう考えた。
Windows 95立ち上げ時、日本のパソコン業界は活況を呈していた。果たして、当時のメーカーは今も残っているだろうか。大和総研のアナリスト時代には、日本の半導体メーカーが飛ぶ鳥を落とす勢いだったが、現在は見る影もない。日本は技術立国と言いながら、他国が開発したものを安く改良して競争に勝ってきただけだ。

日本の伝統工芸はどうか。アメリカが逆さになっても太刀打ちできない、古い歴史がある。しかし、調べてみると伝統工芸の市場は昭和40年代から右肩下がりだ。「日本国内に需要がないのなら、海外で需要を掘り起こせばいい」。実際、日本文化に対する関心は確実に高まっている。海外で注目を浴びれば、日本に逆輸入する道も開ける。ただ、同じことをしていては伝統も廃れてしまう。「これまで伝統が生き残ってきたのは、イノベーションをしてきたからです」
価格がネックなら、シェア・エコノミーのモデルを導入できるかもしれない。中古市場が成熟すれば、高価な着物も生き残れるのでは? 「腕のある職人さんが生計を立てられるようなビジネスモデルと後継者を育てる仕組みが必要」。さすが元経営者だけあって、視点は鋭い。何を変えて、何を残すか。着物の織りや染めの技術が洋服の中に受け継がれていけば、それもイノベーションではないか。明美さんは思案をめぐらせる。試行錯誤の末、2017年に、日本の伝統工芸普及のためのファイブセンシス財団を設立した。
活動の一環として支援する京都伝統工芸大学校は、漆工芸、蒔絵、陶芸、仏像彫刻など10の専攻に分かれ、職人やクリエーターを養成する、学士号取得も可能な学校だ。今年3月には2名の学生を1週間ほどシアトルに受け入れた。「日本の建築デザインや伝統工芸がアメリカ人のライフスタイルにどのように取り入れられているのか、学生たちに肌で感じて欲しい」。いわゆる実地のマーケティング調査だ。

そのひとり、木工を専攻する学生は、東日本大震災のドキュメンタリー視聴をきっかけに、進学校から同校に入ったそう。「釘を使った家具はどれも修復不可能。傷んだ箇所だけ修理すれば使える木工の技術は、サステナブルな社会を考えるうえでとても重要だと思いました」。日本の木工はアメリカでは高級品として人気が高い。和だんすが置かれたアメリカのモダンな住宅を見せたところ、それまで半信半疑だった学生も「人生が変わりました」と感銘を受けた様子だ。
「若い人たちが志す限り、日本の伝統文化に可能性は残されています」。常に自分の物差しを大切に生きてきた明美さんは、そうした若者の支援に確かな手ごたえを感じている。