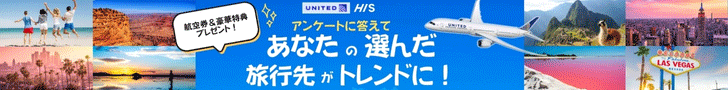藤原定家について、ワシントン大学で公開講演が行われたのは2018年10月25日のこと。講師はアジア言語文学科科長のポール・アトキンス教授です。今でこそ日本文化に深い造詣を持つアトキンスさんですが、初めて渡日した時は、日本についての知識は皆無に等しかったそう。その後いかにして日本への興味を深めていったか、また、定家の魅力とはどんなものなのか、たっぷり語ってもらいました。
取材:ブルース・ラトリッジ 写真:室橋 美佐 翻訳:大井美紗子
百人一首の撰者ではない!?
藤原定家が偉大な理由
「京都行こう」で人生が変わった
「祇園祭に合わせて、日本を初めて訪れたのですが、その当時はひと言も日本語を話せませんでした」
アトキンスさんが育ったのは、映画「サタデー・ナイト・フィーバー」や「狼たちの午後」の舞台にもなった、ニューヨークの下町ブルックリン。そこで、日本文化とは縁もゆかりもない生活を送っていた。作家を志し、スタンフォード大学へ進学すると、英米文学を専攻しながらフィクションと詩作を研究。東アジア文化に初めて触れたのは、大学3、4年生の時だ。きっかけは道教、禅、それに「ビート・ジェネレーション」だったという。
ビート・ジェネレーションとは、西洋文明に反発して東洋文化に傾倒する作家グループで、当時の若者やヒッピーに大きな影響を与えた。ビートニクとも呼ばれ、『路上』の作者、ジャック・ケルアックなどは代表的な「ビートニク作家」だ。若きアトキンス青年は、中でも1950年代に活躍したビート・ジェネレーションの詩人、ゲーリー・スナイダーに憧れた。
スナイダーは50年代後半から60年代後半にかけて日本の京都に滞在し、禅や修験道について学んでいる。スナイダーの影響もあり、大学卒業後は京都へ行こうと決めた。といっても、日本の伝統文化に関するコースをひとつ選択していたくらいで、日本語は全くわからない。「それでも、京都が日本文化の中心地であることは知っていました。しかも京都で毎年7月に開催される祇園祭は、世界一の歴史を持つ祭礼だと。その祇園祭を見ようと思って旅の計画を練ったのです」。大学を出たてのアメリカ人が日本へ長期滞在する方法としては「JETプログラム」がよく知られているが、参加申し込み期限はとっくに過ぎていた。それでも、大学の卒業式を6月中旬に終えると、7月初めには京都の地を踏んでいた。
「計画を立てるのが遅すぎましたね。必要なことは京都に着いてから2週間で全て済ませました。英会話教師の仕事とホームステイ先を見つけ、ビザ発給を受け、日本語レッスンをしてもらうために京都YMCA会員向けの集中日本語コースに登録し、未来の妻となる女性にも会って。これだけのことが、たった2週間でできたんです」
日本への滞在はおよそ2年に及んだ。2年目の祇園祭では、勤務先だった英会話学校の同僚の紹介で、長刀鉾を引く機会にも恵まれた。祇園祭前祭のハイライト、山鉾巡行は毎年くじで巡行の順番を決めるのだが、長刀鉾は「くじ取らず」で、必ず先頭を巡行する名誉に預かっている。「貴重な体験になりました。それに、長刀鉾を引けるのは40歳未満と決まっていますから。若いうちに経験できて良かった」
国際交流団体が主催した京都文化博物館観覧の日のこと。隣り合った京都在住の女性に、能の公演へ誘われた。「詩人のエズラ・パウンドに興味があると言ったんです。パウンドは西洋世界に能を広めた人物。パウンドが好きなら、ということで誘ってもらいました」。以来、アトキンス青年は能に魅了され、足しげく公演へ通うようになる。「能の筋書きは非常にシンプルです。登場人物も、僧女・死霊など、衣装や能面を見るだけでわかるようになっています。英訳と照らし合わせながら話を追っていくうちに、やがて演者たちが何を言っているのか知りたくなりました。英訳ではなく、原文の意味を知りたいと」。そして、アトキンス青年はスタンフォード大学へ戻ることを決意。学士課程では英米文学専攻だったが、修士で選んだのは日本古典文学。修士論文は和歌をテーマにした。そして再び日本へ渡り、東京大学で能に関する調査論文を仕上げ、博士号も取得した。
でたらめと批判された定家の歌

アトキンスさんは、ワシントン大学ケーン・ホールでの藤原定家に関する一般公開講演で、「定家は、日本のT・S・エリオットのような存在です」と語った。日本国民なら誰もが名前を聞いたことがあるくらい重要な人物。しかし、なぜそこまで影響力があるのかをかいつまんで説明するのは、いささか難しいと言うのだ。「エリオットに関していえば、長編詩『荒地』で第一次世界大戦後の社会不安を見事に書き表したから、というのが理由になるでしょうが、定家の場合はどれかひとつ和歌を挙げて作風を語るということが、なかなかできないのです。エリオットと同じく、定家もまた単なる詩人ではありませんでした。批評家であり、理論家であり、編集者でもありました。定家と晩年に親交を結んだ西行は純粋な歌詠みでしたが、定家は違ったのです」
平安・鎌倉時代の歴史人物、藤原定家(1162~1241年)。その名を聞いて日本人が思い浮かべるのは、彼の歌よりもむしろ、『新古今和歌集』や『新勅撰和歌集』の撰者としての一面だろう。そのほかにも『源氏物語』の校訂・研究、歌論書の執筆、日記『明月記』の執筆など、その功績は多方面にわたっている。とりわけなじみ深いのが、『小倉百人一首』だ。冬休みの課題として暗唱したり、お正月に学校や家庭でかるた取りをしたりした人も多いのでは。最近では『ちはやふる』や『うた恋い。』など、漫画、アニメ、映画のテーマにもなっている。一般的には「定家の撰」とされている百人一首だが、アトキンスさんはそれに異論を唱える。「編さん者は定家であると600年以上思われてきましたが、近年になって別の説も浮上してきました。私も、定家が編さんしたとは思っていません。思うに、撰者として誰かひとりを挙げる必要があったのです。名の知られた定家は、代表者としてぴったりだったのでしょう」。では、真の編さん者は誰だったのか。アトキンスさんは、定家の子孫たちではないかと推察する。「『小倉百人一首』の歌は、わかりやすくて覚えやすい。非常にシンプルで、定家の歌風とは真逆だと言えます。定家の歌は技巧に富んでおり、『達磨歌』、つまり禅問答のように難解だとからかわれていました」

インドの達磨によって伝えられた禅宗は、当時の日本ではまだ新しい宗教だった。仏教の一派とはいえ、経典を重視せず、座禅や問答(公案)によって悟りを開くことを目指していた禅宗は、ほとんど邪教扱いされていた。「定家が作る新傾向の歌も、禅問答のようにでたらめだといって批判されたのです。今の時代で『禅』といえば、誉め言葉になるでしょうけどね」。定家の作品には、本歌取り――つまり古歌のキーワードやストーリーを取り入れて新たな歌を作るスタイルが多い。読者は古歌に通じていなければならず、また作品の筋や情景を、頭をフル回転させて考えなければならない。「定家の歌を読む時には、大変な努力が要ります。でも努力なんかしたくない、単純明快がいちばんだという人もいるでしょう。そういう連中が定家を『でたらめ』呼ばわりするのです。定家だったら、『私の歌はでたらめの禅問答ではなく、深淵なる密教なのだ』とでも言うでしょうね。実際、定家の著作物の中にはそうした反論があります。『歌に通じている者なら、私の歌を理解できるだろう。知識がある者は口をつぐみ、無知な者だけが無駄口を叩く』とね」
日記と書、これが定家を
定家たらしめている2つの要素
『明月記』こそ定家の真価

定家の遺した日記『明月記』は、後年名前が付けられたものだ。定家自身はそれを「愚記」と呼んでいた。55年もの長期にわたって克明につづられており、3分の2が消失してしまっているとはいえ、当時の生活や宮中での動向を伝える貴重な資料となっている。平安・鎌倉時代、多くの公家たちが日記を遺しているが、定家の『明月記』はそれらと一線を画す。「なぜなら『明月記』には、定家の感情が生き生きとつづられているからです。当時の日記というのは、この儀式の時には誰それがいて、衣装はどんなで、これだけ領土をもらって、と事実を記録するのが目的でしたが、定家はそういう書き方をしませんでした。その場に座し、自分の内面と向き合って言葉をつづっていたのです」
たとえば、明日で70歳を迎えるという夜のこと。この時代に齢70を迎えることがいかに稀有であるか、と定家はしみじみ噛みしめている。「父方の家族で70まで生きられたのは誰だったろう、と記録を調べています。それだけではなく、親戚たちがどこまで出世したかも気にしています。定家は官位への執着がとてつもなく強い人でした」。定家は昇進が遅かった。しかし、70歳の時に権中納言になる。「自分にしては上出来、と思っていたことでしょう。定家は生来病弱で、そのことを死ぬまでぐちぐちと嘆いていました」。結果的に定家は80歳まで生きた。歌道や出世レースのライバルたちよりもずっと長生きしたのだ。「定家は気難し屋だったと言われていますが、果たして本当にそうだったのでしょうか。単に自分に正直なだけだったのだと私は思います。ほかの人は聞こえのいい言葉を著作に並べていましたが、定家は違いました」。実際『明月記』には、出世へのこだわりや他人の悪口が多く見られる。「定家の偉大さは、自分の感情を赤裸々につづっている点にあります」
「鬼のような字」に自信

定家は、書家としても人並外れた作品を遺している。「彼の手書き文字は非常に読みやすいのですが、お世辞にも美しいとは言えません。たとえば彼の父、藤原俊成の筆跡のように、針金を思わせる鋭い緊張感というものは、定家の字にはありません。定家は徹底して、文字の読みやすさ・正確さを目指したからです」。定家は当時の人物としては真跡および伝称の筆跡が極めて多いのだが、それは彼が途方もない量の文字を書写したからにほかならない。「パソコンはおろかタイプライターもコピー機もない時代、人々は1冊の本をまるまる手書きで写し取っていました。大量の紙と墨、それに時間も必要ですね。年を取るにつれ、定家の筆跡はどんどん崩れていくのですが、そこには艶というか、真のオーラというものが宿っています。定家自身は自分の筆跡のことを『鬼のような字だ』と『明月記』に書いているのですが、読みやすさと正確さについては自信を持っていました」
日記と書、これが定家を定家たらしめている2つの要素である。「定家は、現代人にも非常に親しみやすい人物です。年齢を重ねてからの書には、筆舌しがたい哀愁が漂っていると思うのです」
ポール・アトキンス(Paul Atkins)■ワシントン大学アジア言語文学科科長。研究対象は、古典・前近代の日本言語・文学、前近代のアジア研究・演劇・詩、およびそれらの翻訳作品。2017年、『Teika: The Life and Works of a Medieval Japanese Poet』(ハワイ大学出版)を上梓。スタンフォード大学で学士・修士・博士号を取得。
※同記事の英文記事はこちら