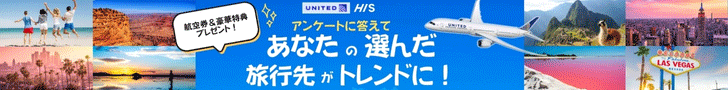いつも朗らかな印象で、手芸と社交ダンスを日々の楽しみとするテラオ清子さん。最初に日本からシアトルに来たのは、1959年のことでした。戦前の日系移民と区別し「新1世」とも呼ばれる日本からの米国移住者。その先駆けである清子さんは、どのような経験をしてきたのでしょうか。1941年12月7日の真珠湾攻撃による日米開戦から間もなく80年。戦争のこと、渡米の経緯、仕事、そして現在までの暮らしについて振り返ります。
いつも朗らかな印象で、手芸と社交ダンスを日々の楽しみとするテラオ清子さん。最初に日本からシアトルに来たのは、1959年のことでした。戦前の日系移民と区別し「新1世」とも呼ばれる日本からの米国移住者。その先駆けである清子さんは、どのような経験をしてきたのでしょうか。1941年12月7日の真珠湾攻撃による日米開戦から間もなく80年。戦争のこと、渡米の経緯、仕事、そして現在までの暮らしについて振り返ります。
取材・原文:デイビッド・ヤマグチ 翻訳:宮川未葉
写真:『北米報知』より転載
※本記事は『北米報知』2021年4月23日号に掲載された英語記事を一部抜粋、意訳したものです。
テラオ清子■愛媛県今治市で生まれ育つ。戦後は洋裁を学び、東京で洋裁師として働いていたが、姉の子育てを手伝うため、キャリアを中断して1959年にシアトルへ。一時的な滞在の予定が、友人を通じて見合いをした日系2世の男性から結婚を申し込まれ、長い移民生活が始まることに。18年前に夫が他界するまで、添い遂げた。手芸と社交ダンスが趣味。
日米開戦で女学生生活は一変
清子さんは愛媛県今治市の出身で、9人兄弟の7番目の子ども。父親は着物の家紋入れを仕事にしており、父親が紋を描き、一家の女性たちがそれを刺繍した。「いいビジネスでした」と、清子さんは言う。父親は子どもたち全員に高等教育を受けさせようとしていた。清子さんも今治精華高等女学校(現・今治精華高等学校)に進んだが、第二次世界大戦は、清子さんの女学生生活に大きな影響を及ぼした。

(米空軍資料、1952年)
「男性たちは次々に出征していき、男手が少なくなったため、私や同級生たちは、それまでしたことのなかった稲刈りの手伝いなどをしました。夜は灯火管制が敷かれていたので、光が漏れないように押し入れに入って勉強しました。日米開戦1年目はそれほどでもなかったのですが、その後の3年間は少しずつ大変になっていきました」

1945年8月6日には、広島に原子爆弾が落とされた。今治はその数時間前まで、米軍のB-29による焼夷弾攻撃を受けていた。8月5日夜中から続いた今治空襲だ。今治では旧市内の約8割が焼失した。日本政府が降伏の意思を連合国に電報で知らせたのは、そのわずか4日後、8月10日のことだった。

空襲の夜、清子さんは家族と山の洞穴に避難していた。父親ひとりが残り、家を守っていたが、焼夷弾で起きた火事を消そうとしたものの消せないと悟って逃げたと話す。「ひと晩で宿なしになってしまったの」と、清子さん。
住む家がなくなった次の夜、一家は仕方なく浜辺で寝た。盛夏のことで、蚊の大群に悩まされた。やがて近くの学校に一時避難したが、ほかにも家を失った多くの家族が避難してきていた。「近くで子どもが泣いていたりして、なかなか寝られませんでした」。今治は広島と瀬戸内海を隔てて隣り合うが、原爆投下時には何も見えなかった。しばらくして、広島で負傷した人々が助けを求めて小さな船で今治に来るようになった。
我慢、我慢の敗戦直後
学校の避難所には1カ月ほどいた。その後、9月の学校再開に合わせて一家は立ち退かなければならず、今度は銭湯で間借りすることに。その銭湯の建物はコンクリートでできていたため、空襲に遭っても焼け残った。夜は浴室のタイル敷きの床に寝た。

生活は困窮していた。一家は家の焼け跡に戻り、食べ物と交換できる、生活の足しになるような物を探した。「兄が以前に掘った庭の防空壕に着物が残されていたので、それを田舎に持っていき、農家で野菜と交換してもらいました。当時、農家の人はお金ではなく、着物を欲しがっていました」。それでも、食べ物は十分とは言えなかった。「いつもお腹をすかせていたことを覚えています」。電気は何年も使えなかった。ろうそくを使ったり、皿に入れた食用油にひもで作った芯を浸して火をともしたりしていた。「焼け残った家の窓明かりを見ては、うらやましく思いました」

両親は、バラック小屋のようなものを自分たちで建てた。今の日本では、2011年の東日本大震災のような大きな災害が起こると、政府が都市の復興や被災者の支援を助けるが、当時は違った。「日本は第二次世界大戦で敗戦したのです。家も食べる物もない中、支援の当ては全くありません。だから、我慢、我慢でした」と、清子さんは言葉を重ねる。
新1世の波
戦争が終わって、清子さんが新たに始めたことがある。洋裁の勉強だ。片道1時間半かけて松山洋裁女学院(現・松山ビジネスカレッジ クリエイティブ校)に2年間通い、洋裁師になるための訓練を受けた。1950年代後半には東京で洋裁師としてのキャリアを築いていた。

日本で日系2世の男性と結婚し、航空会社で働く夫の仕事の都合でシアトルに渡っていた姉から、4人の子の世話を手伝って欲しいと言われたのはその頃。1959年、清子さんは初めてシアトルにやって来た。「アメリカに来るつもりはなく、来たいと思っていたわけでもなかったのですが、共働きでベビーシッターを必要としていた姉の再三の頼みを無下にはできず、洋裁を学ぶことにして学生ビザを取りました。アメリカに着いたのは、サンクスギビング前日でした」
このシアトル滞在中、清子さんに大きな転機が訪れる。英語を習う先でできた友人を通して見合い話が持ち上がり、父母は共に広島出身という日系2世のマサシ・テラオさんから結婚を申し込まれたのだ。期間限定のはずだったアメリカ生活は、現在までずっと続く長いものになった。

東京で洋裁師をしていた経験もあり、働き口はすぐに見つかった。25年間勤め上げたライトハウス・フォー・ザ・ブラインドでは、主に米軍から発注された縫製の仕事をしていた。軍服のネクタイほか、海軍の軍艦旗も作った。ネクタイの縫製は、ひと束48本ごとの出来高払い。「私が48本のネクタイをどれくらいの時間で作れたかわかる? 15分よ!」と誇らしげに語る清子さんは、作業が特に速い3人のうちの1人だった。スピードだけでなく質にもこだわって頑張る清子さんは、上司から「そんなに上手に作らなくていいから」とよく言われていたそうだ。得意の洋裁を日系人女性たちに自宅で教えたこともあった。
1世、2世、帰米、戦争花嫁と、日系社会の構成は時代と共に変容していくが、清子さんはその次のグループである新1世の最先端にいた。新1世は、戦後にさまざまな個人的理由で新たにアメリカへ移住してきた人々だ。日本人や他のアジア人の移民を停止した1924年の排日移民法以来、非白人に立ちはだかっていた障壁は、1965年の移民国籍法によって取り除かれた。そのため、ほとんどの新1世は60年代半ばになって米国に来ている。家の事情や生活の保障などのためではなく自らの意思で祖国を離れ、アメリカに移り住む日本人たち。清子さんのような人々が起こした新しい波は、現在も続いている。
とにかく手で物を作り出すことが楽しい
「日本の夢は見ますよ。夫の夢は見ないけれど(笑)。昔の同級生が夢に出てきます。同級生たちとはこれまで何度か集まりましたが、今はもうないですね」

この12月には94歳になる清子さん。今でも手を動かして何かを作り出すことが大好きだ。ほかの人がもらってもとまどうようなささやかな物も喜んで受け取り、アレンジを施す。たとえば、バケツいっぱいのプラムはジャムに、大量にもらったアウトレット店のパンはトーストやサンドイッチに、下の世代の友人が親の家を片付けて見つけた毛糸や布は帽子や毛布、ルームシューズ、エプロンに、といった具合。そうした手作り品は仲間への素敵なお返しやギフトとなって循環している。
 もうひとつの楽しみは社交ダンスだ。2世復員軍人会(NVC)ホールの社交ダンス教室では、日系3世の若い友人が大勢できた。焼け野原になった戦後の今治で、社交ダンスが唯一の楽しみだったことから、それを再開しようと通い始めた。パンデミックで中断されてしまったのが惜しいと清子さんはこぼす。
もうひとつの楽しみは社交ダンスだ。2世復員軍人会(NVC)ホールの社交ダンス教室では、日系3世の若い友人が大勢できた。焼け野原になった戦後の今治で、社交ダンスが唯一の楽しみだったことから、それを再開しようと通い始めた。パンデミックで中断されてしまったのが惜しいと清子さんはこぼす。
持ち前の明るさとバイタリティーでパンデミックを乗り切ろうとしている清子さん。「テレビを見る時もただ座っているだけではなく、常に手を動かしています。春にはまた畑仕事も始まります」と、毎日を忙しく過ごす。友人とはよく散歩に出かける。「中華系の彼女は、料理がとても上手。散歩のたびに、残り物だと言って料理を手渡されます。今は住まいもあって、食べ物もたくさん。アメリカ人は食べ物を無駄にして、もったいないですね」