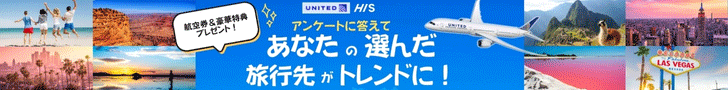工藤拓哉さんインタビュー
「懐の深い人」という印象。世界最大のコンサルティング会社、アクセンチュアでデータサイエンス部門の統括をする工藤卓哉さんは、名立たる企業のトップとつながり、助言を求められる立場に。「データが好きなんです。勘ではなく、データに基づいて意思決定をすることが」と、目尻を下げます。頭に入っている膨大な情報と共に、ソフトな口調で語ってくれました。
取材・文:渡辺菜穂子
写真:アクセンチュア、ARISE analytics、本人提供
工藤卓哉■愛知県出身。1997年に慶應義塾大学商学部を卒業し、アクセンチュア株式会社に入社。2004年に退社し渡米。2005年にコロンビア大学で国際公共政策修士号、2010年にカーネギーメロン大学で情報技術修士号を取得。また、ニューヨーク市で統計ディレクターを務める。2011年から2014年まで東日本大震災の震災支援に関わる。2014年にシアトルに移住し、現在はアクセンチュア・データサイエンスセンターのグローバル統括として活躍する傍ら、株式会社ARISE analytics(アライズ アナリティクス)取締役を務めている。
データでどう世の中を救う?
データサイエンスを利用したコンサルティング業というのは、具体的に何をしているのだろうか。多くの事例は企業秘密に関わるため、なかなか表に出てこない。そんな中で話題となり、ビジネス誌『フォーチュン』の「Change the World(世界を変える企業)」にも紹介されたのが、佐賀県の救急車搬送システムを改良した件だ。その事例からデータサイエンティストの仕事内容を説明してもらった。
 「まずは課題があります。佐賀県の場合は当時、救急車を呼んでもいわゆる『たらい回し』などで患者がスムーズに病院に運ばれないと相談を受けました」。もともと高齢化社会で医者も救急車も少なく、そのうえ、市町村統廃合により管轄エリアの道順がわからないというケースも発生していた。搬送に時間がかかれば患者の死亡率が高まり、受け入れを拒否する病院がより増えるという悪循環。
「まずは課題があります。佐賀県の場合は当時、救急車を呼んでもいわゆる『たらい回し』などで患者がスムーズに病院に運ばれないと相談を受けました」。もともと高齢化社会で医者も救急車も少なく、そのうえ、市町村統廃合により管轄エリアの道順がわからないというケースも発生していた。搬送に時間がかかれば患者の死亡率が高まり、受け入れを拒否する病院がより増えるという悪循環。

「次に、いろいろな方面の関係者から話を聞きます」。救急車は、要請依頼を受けた緊急センターが車両を配車。現場に到着した救急救命士が状況判断をして病院に電話し、受け入れの承諾が得られたら搬送となる。「つまり、そこで救急救命士の勘に頼るところが多いのです。たとえば心臓発作の場合は、心臓外科医と手術設備が整っている病院を瞬時に判断したいのですが、経験の浅い救急救命士には難しい。1回電話して断られると1分20秒ロスすることがわかりました。心臓発作だと1回のロスで脳死状態になってしまいます」
多方面から情報を集めて現状を把握した後に、いよいよデータが登場する。「現在人間が担っている意思決定プロセスを、なんとかデータでシステム化できないかと考えます」。佐賀県のベテラン救急救命士が電話する時に思い浮かべるのは、病院の設備、専門医の有無と勤務スケジュール、病床が空いているかどうか、現在地からの距離。それらの情報をデータ化し、「心臓発作」と打ち込むと、最適な病院までの道順が示されるプログラムを作成して、iPadに搭載した。
このように、データに基づいた意思決定システムは迅速さと確実性を高める。佐賀県の事例はモデルケースとなり、日本全国に拡大している。データサイエンスで人を救うことができるのだ。
データサイエンスはコラボレーション
佐賀県で用いられたデータサイエンスの力は東日本大震災の復興支援にもつながっている。「九州佐賀県の緊急車両システムは、東北福島県の若者によってプログラミングされたのです」と工藤さん。
 工藤さんは2011年から2014年の間、日本に移住し、被災地の復興支援に携わっている。福島県会津若松市にアクセンチュア・イノベーションセンター福島センターを、アクセンチュアで共に働く中村彰二朗さんと立ち上げた。中村さんは現在、同センター共同統括を務める。「被災地が本当の意味で復興するには雇用の支援が必要です。それがないと人が戻って来ません。データサイエンスは、クラウド・コンピューティングさえ使えれば仕事になるので、雇用の起爆剤になると思いました。震災で打撃を受けた会津若松から、世界を救うことができるのです」。効果は大きかった。今や会津若松は、日本有数のスマート・シティーとして、経済産業省や民間企業などの視察があとを絶たない。
工藤さんは2011年から2014年の間、日本に移住し、被災地の復興支援に携わっている。福島県会津若松市にアクセンチュア・イノベーションセンター福島センターを、アクセンチュアで共に働く中村彰二朗さんと立ち上げた。中村さんは現在、同センター共同統括を務める。「被災地が本当の意味で復興するには雇用の支援が必要です。それがないと人が戻って来ません。データサイエンスは、クラウド・コンピューティングさえ使えれば仕事になるので、雇用の起爆剤になると思いました。震災で打撃を受けた会津若松から、世界を救うことができるのです」。効果は大きかった。今や会津若松は、日本有数のスマート・シティーとして、経済産業省や民間企業などの視察があとを絶たない。

「この業界に興味のある仲間を募集しています」と話す工藤さんに、どういう人が向いているのかを聞いた。「僕はデータが好きで数学が得意ですが、あまりそこを押し付けるつもりはありません。ひとつの領域にこだわらずに、何でも学べる人がデータサイエンスに向いているのではと思います。フランス文学を専門としていた人が、トップクラスのデータサイエンティストになった例もあります。逆に、ハーバード大学で物理学の博士号を取っていたとしても、人とコミュニケーションが取れないとダメです。『データサイエンスは何か』と聞かれたら『コラボレーションです』と答えています。上下関係やバックグラウンドの違いにとらわれず、積極的にいろんな人から学ぶ姿勢が必要とされる仕事です」
インディ・ジョーンズと父親に憧れて
子どもの時はインディ・ジョーンズに影響を受けて、考古学者になりたかったと話す工藤さん。大学の卒業時は、「決められた枠組みで仕事をするのではなくて、誰も解いたことのないパズルを解くように働けるのがコンサルティング業」と確信し、アクセンチュアに就職を決めたそう。「コンサルティングもインディ・ジョーンズも、答えのない状況から何かを探し求めていくという意味で共通しています。危険なところにも勇敢に飛び込み、世界中を旅行しながら未知への挑戦をしています。天職だったかなと思っています」

しかし、28歳で退社し、アメリカに留学した。それは父親の影響が大きかったと言う。消防署長だった父親は、ある日、叙勲旭日章をもらうことになった。「天皇陛下から旭日章をもらえるんだよ」と言う父親の顔が、生き生きとして見えた。「当時の自分は枯れていました。マネジャーになり、コンサルティング業務はルーティン化。このままでは30年後に父のように輝いていられないと思いました。それまで利益追求の仕事をしてきたので、人の命を救うような公共政策をやりたいと」
迷わず選んだ新しい道は、その後も一貫している。コロンビア大学で国際公共政策の修士号を取得し、ニューヨークのマイケル・ブルームバーグ市長(2002年〜2013年任)の元で働き始める。ニューヨークの格差社会は深刻だ。データサイエンスを用いて、メディケア、メディケイド対象の人々でも確実に医療を受けられるサポートシステムや、一部の公立校の腐敗を正すためのデータによる透明性の高い客観的評価システムを構築した。

そんな頃に、東日本大震災が起きた。大混乱となっていた日本に「データに基づいた意思決定」の必要性を工藤さんは感じた。行動は迅速だった。日本に移住することを決め、家族を説得し、古巣であるアクセンチュアに打診をし、ニューヨークで所有していた家を処分。2011年5月には復興支援プロジェクトに手をつけていた。「妻にはすごく嫌がられました。日本に行ったこともない白人のアメリカ人です。しかも当時は、メルトダウンを起こして余震も止まらない状態。一応納得して仕事も辞め、ついてきてくれたのですが」
そんな家族の事情もあり、震災復興にある程度貢献できたと感じた段階で再び日本を離れ、2014年12月にシアトルに引っ越した。冒頭で紹介した佐賀県の事例は、工藤さんがシアトルから会津若松に指示を出し、プログラミングを仕上げた。「シアトルは子育て環境も整い、圧倒的に住みやすいですね。世界の通信パケットの70%を占める巨人企業があるので、データサイエンティストとしても、いい拠点です。マイクロソフト、アマゾン、グーグルなどパートナー各社にも10分程度で行けるし、日本にも近いし、おいしいコーヒーもあるし」
ノミと子どもと仕事の可能性
個人的に今後やりたいことを尋ねてみた。「教育系ですね。今はまだ自分の子どもに精一杯なのですが、10年先くらい、退職した頃にでも。日本人ですから、日本に貢献したいです。内向きになっている若い日本人たちが、もったいないなぁと思います。

アメリカで働く日本人として、自分がやってきたことを多くの若い人たちに伝えたいという気持ちがあります。あと痛ましいのは日米共通ですけれど、日本は特に18歳以上の孤児に向けた国としての制度設計と支援の仕組みがないので、そこを支援するシステムができないかと考えています。すごく恵まれた環境にあるはずの自分の子どもたちが文句ばかり言うので『水も飲めない子どももいるのに』とよくさとすのですが、口にしている以上、支援もしなければと」
家庭ではどんな父親なのだろうか。「子どもには厳しいと思います。妻が優しい分、バランスを取るようにはしています」。子どもたちは興味を持って何かを始めるものの、飽きてはすぐ興味の対象が移ってしまうそうだ。習い始めたバイオリンをやめた時には、「自分が子どもの時は、バイオリンなんて高いものは……」と嘆いたことも。

「妻からは『自分と比較したらダメ、比較すると枠組みの中に収まってしまい、大きくなれない』と言われました。確かにその通りだと思いました。特に日本の男性は、固定概念の強い人が多い気がします。日本に帰ると、子どもの失敗に真剣にキレている男親が目につきます。僕は自分では柔軟なほうだと思っていますが、それでも日本人男性です。だから、妻に言われることは素直に受けるようにしています」
工藤さんはデータサイエンスに関する講演をする時、ノミの話をよくするそうだ。ノミは小さいのに何十センチも飛び上がれる。しかし、コップに入れて1日育てると、コップの高さしか飛べなくなってしまう。「仕事も子どもも同じです。親やほかの子と比較すると、その高さしか飛べなくなってしまうから、絶対にしてはいけないのだなと思います。アメリカではよく言われますが、日本にいたら到底学べなかったことです」