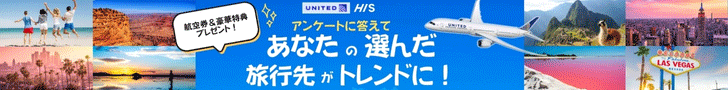切り絵作家 曽我部アキさん
美しいマウント・レーニアや、満開の桜の向こうに顔をのぞかせるスペース・ニードルなど、どこか日本を思わせる素朴なタッチでワシントン州の風景を切り取る曽我部アキさんの作品は一度目にしたことがあるのでは。シアトルを代表するアーティストの創作の源はどこにあるのでしょうか。制作の裏側を探ります。
取材・文:加藤 瞳
写真:本人提供
 曽我部アキ■静岡県出身。ベルビュー在住。1978年の渡米後、プロのアーティストとして活動開始。ワシントン州内30以上の公立校に作品が展示されているほか、パイクプレイス・マーケットの壁画、宇和島屋シアトル店エントランスの鉄塔など、パブリック・アートも数多く手がける。ベルビュー美術館のアート・フェアには1983年のエントリー以来37年連続で選出(2020年はコロナ禍のため開催中止)。姉妹紙『北米報知』にて1998年より「今月の切り絵」コーナーを持つ。 www.akisogabe.com
曽我部アキ■静岡県出身。ベルビュー在住。1978年の渡米後、プロのアーティストとして活動開始。ワシントン州内30以上の公立校に作品が展示されているほか、パイクプレイス・マーケットの壁画、宇和島屋シアトル店エントランスの鉄塔など、パブリック・アートも数多く手がける。ベルビュー美術館のアート・フェアには1983年のエントリー以来37年連続で選出(2020年はコロナ禍のため開催中止)。姉妹紙『北米報知』にて1998年より「今月の切り絵」コーナーを持つ。 www.akisogabe.com
いつもアートがそばに
「プロのアーティストなんて、なろうともなれるとも思っていなかった」。そう語るアキさんだが、その半生は常にアートと共にあった。
静岡県に生まれ、富士を望む環境でのびのびと育った子ども時代。活発だったアキさんは男の子ともよく遊んだ。お絵描きも得意で、地元の風景をスケッチしたり、手塚治虫氏による『リボンの騎士』など好きな漫画を読んではまねして描いたりした。当時の様子がよくわかるエピソードがある。「昔、家の襖に、うさぎとカエルが相撲を取っている鳥獣戯画をまねして描いたことがあるの。でも、全然怒られなかったどころか『うまいね、アキちゃん』なんて言われて。すごく面白かったのを覚えています」
やがて就職が決まったのは、アートとは程遠い遺伝学研究所。アキさんは人類遺伝学教授のアシスタントとして働き始めた。そして、ハワイ大学での研究活動に同行した際に現地で出会った日系アメリカ人と、その後結婚することになる。

夫は船舶会社に勤めていた。シンガポールへの駐在が決まると、アキさんはそのままずっと外国暮らしの身となった。海外生活での育児に奮闘する中で、アートは変わらず心のよりどころだった。「結婚前に、当時流行り始めたフラワー・アレンジメントを習って資格を取っていたんです。シンガポールでは近所の子に絵を描いたり、お花を作ってあげたりと、いつも子どもたちと触れ合っていた楽しい思い出があります」
そんなアキさんに、地元のデパートから「お花を売りませんか?」とのオファーが舞い込んだ。話はとんとん拍子に進み、300束ほどのブーケを作り、販売するようになる。それでも、いつもちょこちょこと何かを作っているのが好きだったアキさんは、あくまで趣味の一環として、自分が楽しいからやるというスタンス。「プロになろうだなんて全く思っていなかった。まあ、子育ても大変だったんですけれどね」と、笑いながら振り返る。
歯科医院で人生の大転換
1978年、シンガポールからシアトルに移住した。そこでひょんなことから人生が大きく変わることになる。

ちょうど切り絵を始めた頃だった。「最初はちぎり絵でした。でも、すごく細かいんですよ。面倒になって切り絵に(笑)」。山下 清作品に感銘を受け、「面白そう!」と始めたという当時のちぎり絵作品を見せてもらうと、その完成度に目を見張る。切り絵は滝平二郎作品や中国の切り絵細工、また芸術的には葛飾北斎の影響が大きいと言う。「富嶽三十六景を初めて見て、なんでこんな絵が描けるんだろうって。北斎は漫画家でもあり、ちょっとした表情や体の姿勢が本当に素晴らしくて、いろんなことを学びました」
始まりは、歯科医院の待合室でのたわいない会話からだった。「受付のおばさんの趣味が水彩と言うので、私も切り絵をやるって応えたら、『そんなの見たことがない、今度持ってきて』って」。次の来院時、アキさんは切り絵とちぎり絵を1点ずつ持参した。そこにちょうど居合わせたのが、歯科医の妻と歯科器具販売員の男性だった。「奥さんがね、『これ、いくら?』って聞いたの。とっさに50ドルと返すと、奥さんもその男性もパッと買ってくれたんですよ。え、売れるの……って、心臓がドキドキしました。帰り際、受付のおばさんも、『あなた、絵をおやりなさい。売れるわよ』と。おばさんの後押しで私はアーティストになったのかな(笑)」
 しかし、アキさんは「絵が売れたのは珍しいから。思い上がってはいけない」と、自分に言い聞かせていた。当時、アーティスト活動を始めながら語学学校で日本語を教える仕事も続けており、育児との両立に苦労していたアキさん。「若かったからできたんだなぁ、頑張ったなと、今は思います。子どもたちは私が賞をもらうと、ものすごく喜んでくれました」
しかし、アキさんは「絵が売れたのは珍しいから。思い上がってはいけない」と、自分に言い聞かせていた。当時、アーティスト活動を始めながら語学学校で日本語を教える仕事も続けており、育児との両立に苦労していたアキさん。「若かったからできたんだなぁ、頑張ったなと、今は思います。子どもたちは私が賞をもらうと、ものすごく喜んでくれました」
運命の出会いから絵本挿絵画家に
絵本挿絵画家として受賞歴を持つアキさんが、初めて絵本制作に携わったきっかけもまた、運命的なものを感じさせる。

当時在籍していたアーティスト団体、イーストサイド・アソシエーション・オブ・ファインアーツ(現エバーグリーン・アソシエーション・オブ・ファインアーツ)のメンバーがオレゴン州フッドリバーへ移住してギャラリーをオープンすることになり、そこに作品を5、6点置かせて欲しいと依頼された。そして、その小さなギャラリーでたまたま作品を見かけたという出版社の編集者から手紙が届いたのだ。新人の絵本作家とイラストレーターによる新刊の出版を企画しているので、もっと作品を見せて欲しいという内容だった。
アメリカの絵本についてあまり知らなかったアキさんは、まず出版事情に詳しい知人に相談した。すると、「すぐに返事を書きなさい。これは有名な会社で、イタズラじゃないわよ」と、背中を押された。手紙の主は出版社、ハーコート・ブレイスに勤める編集者のリンダさん。普段は通らない田舎道でコーヒー1杯のために偶然立ち寄った小さなホテルの隣が、そのギャラリーだったのだそう。実際にほかの作品を見てもらうと、リンダさんから「すぐに連絡します」と言われ、「やった!」とアキさんは手応えを確信。「その時、運命の扉が開いたと感じましたね。そこから始まったんです」
出版後、全米で行われる司書ミーティングに次々と足を運んだ。「シカゴやニューオーリンズ、いろんな街を旅しました。あの頃はすごく楽しかったし、うれしかったですね。地元のアート・フェアに参加しても、範囲が狭いわけですよ。絵本の場合は全米で売ってくれる。アメリカ中で誰かが読んでくれる喜びがありました」
作品作りは「お客さま第一主義」で

制作に当たって大切にしているのは、買い手となる「お客さま」だと強調するアキさんは、いつも感謝を忘れない。ある年、ベルビュー美術館のアート・フェアで、オリジナル作品を注文した女性がいた。やっと子どもが大学を卒業し、生活に余裕ができたので、念願だったアキさんの絵を買うことに決めたと言う。「本当にうれしかったから、お祝いに、かなりおまけしてあげました(笑)。ありがたいじゃないですか。絵なんて、食べ物と違って、なくてもいいものなんだから。そういう感謝の気持ちで作るの」
人気作家でありながら、その謙虚な姿勢が印象的だ。「作ったあとは、自分の絵を2、3日経ってから見る。そうすると『何これ、ここがおかしいや』っていうのが見つかる。『人前に出せない!』なんて絵は何枚もありますよ。作品は愛しているけれど、うぬぼれない、満足しちゃいけない、という精神でいます」。何枚か絵を作ると必ず壁にぶつかる時期がやって来る。自分の作品を卑下すると、息子に「そんなことはない。これがいいって言うお客さんもいるはずだ」と叱られることも。「こんな絵でいいのか、全然上達していない、と悩むことはしょっちゅう。でも、夕飯のおかずを作っていても何をしていても、結局は頭のどこかで次の絵のことを考えている。とにかく続けて続けて、次はもっと良いものを作ろう、お客さんに喜んでもらおうって、いつもそれだけです」

ストップしたら終わりだと、常に走り続けてきた。「月の絵がとても好きなんです。月の昇り始める頃の木々の風景を見て、昔はドライブしながら、『いつか、こういう絵を切りたいな」とよく言っていたのですが、最近は夜景を見ると息子が『お母さんの切り絵みたい』と言ってくれます。こういう絵が切れるようになったんだなぁと思います」
アーティストとしてのチャレンジ
2016年、ワシントン州日本文化会館(JCCCW)による「シアトルのハントホテル」展のプロジェクトに参加した。第二次世界大戦後に強制収容から帰還した日系人が、日本町にあったシアトル国語学校(1902年設立の全米最古の日本語学校で、現在のシアトル日本語学校)の建物をハントホテルと名付け、仮住まいとした1945年から1959年の歴史を掘り起こすプロジェクトだ。当時の写真はその多くが消失しているため、実際に居住した日系人の証言などから、アキさんの切り絵でその様子を再現した。

「当時を知らないから、こういう絵を描いてくださいって言われても大変なんです。まず、どんな服装だったのかがわからない。帽子ひとつにしても今の人たちとは違う。でも、探すと家族写真は割とあるんですよ。それよりも、生活風景の資料がない。何回も何回もスケッチを繰り返しました」。ハントホテル展の作品は1冊の本としてまとめられている。「新しい本の香りをかいだ瞬間、やって良かったという充実感に満ちあふれますね」

チャレンジングなことが好きだと話すアキさん。アーティストは少なからずそういうところがあるものだと続ける。「これまでの自分の作品でいちばん好きなものを聞かれて『ネクスト・ネクスト・ワン』と答えました。ピカソがね、そう聞かれて『ネクスト・ワン(次の作品)』と言ったんですよ。次はもっとうまくやってやるという気持ちが、何かものを作る人には絶対にある。だから私も、ピカソをまねしてみたの。新しいことに挑戦するのは、大変ですけれど」と笑う。
コロナ禍での活動はどうだろうか。「ほとんど変わらないです。コロナ下の生活になってから絵がダメになったとか、描きづらくなったとかも一切ない。むしろこの機会にもっと作ろうと思いました」。アート一色。意気込むその頭の中はいつも作品のことでいっぱいだ。切り絵にはX-ACTO(エグザクト)ナイフのNo. 11を愛用している。「1日に1回、ナイフを持って5分でもいいから指を動かさないと気持ちが悪いんですよ」。制作中はジャズや、最近ではスマートフォンからいろいろな朗読を聴くのがお気に入りだ。「友だちが天童よしみのCDをくれて、切りながら聴いてみたけれど、これは合いませんでした(笑)」

今が本当に楽しいと語るアキさん。「今までやってきたこと、学んだことを毎日楽しめるのは幸せなこと。このままずっと続けていきたいですね」