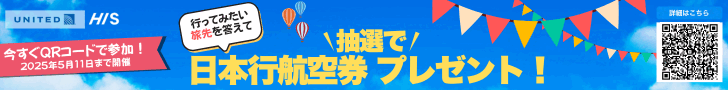人種差別と偏見
敗戦国である日本の女性と、アメリカ軍人との結婚は容易ではなかった。ツチノさんの家族はもちろん大反対。最終的には親族会議まで開かれた。しかし、こうと決めたらテコでも曲げないツチノさんの気質を誰よりもわかっていたのも家族だった。マイクさんが日本に配属された時から、「日本人の嫁を連れて帰らないように」と言っていた祖母は、当然反対だった。しかし、海軍隊員として沖縄戦を経験したマイクさんの父は、意外にも「素晴らしいこと」と賛成してくれたそう。最初は反対したマイクさんの母、そして祖母も最後には「いい奥さんを見つけたね」と言ってくれた。
当時、結婚には軍の許可が必要だった。しかし、日本人との結婚に反対した軍上層部によって、マイクさんは突如バージニア州の基地に転任させられてしまう。転任命令後2週間以内に日本を離れなければならなかった。離れている間、マイクさんはツチノさんに毎日手紙を書いた。ツチノさんのために小さなダイヤの指輪を購入し、宅配荷物の中のボディー・パウダーに隠して日本に送った。
マイクさんのこの突然の転任に腹を立てたのはマイクさんの母だった。ツチノさんとの結婚に反対だったことはさておき、息子が軍から不当な処遇を受けているとし、マイクさんの母は、当時のアイゼンハワー大統領に手紙を書いたのだ。民主党のニューヨーク女性政治会の会長を務めていた祖母の政界への影響力もあり、4カ月の後、マイクさんに沖永良部島行きの指令が下りた。
 ツチノさんの沖永良部島行きを、ツチノさんの家族に認めてもらえるよう、ふたりは軍の許可を待たずに福岡の櫛田神社で挙式。これが後に発覚し、マイクさんが軍事法で査問にかけられたこともあった。 沖永良部島では、未だ許可を得られていなかったため、マイクさんは、終業後いったんツチノさんの待つ家でふたりの時間を過ごし、軍の門限に合わせ基地に戻る、そして夜は別々に過ごす、そんな生活を余儀なくされた。マイクさんは南部出身の同僚から「ニガー・ラバー」と呼ばれたことがあったそうだ。ニガーとは黒人を蔑視する言葉だが、当時の人種差別の激しさを推し量ることができる。一方でツチノさんは、マイクさんと結婚したことで、日本人の子どもたちから、「パンパン」とはやしたてられたことがあったと言う。パンパンとは、主に戦後に駐軍していた人たちを相手にした売春婦のこと。ツチノさんのような「戦争花嫁」たちは、このような偏見に日々さらされていた。
ツチノさんの沖永良部島行きを、ツチノさんの家族に認めてもらえるよう、ふたりは軍の許可を待たずに福岡の櫛田神社で挙式。これが後に発覚し、マイクさんが軍事法で査問にかけられたこともあった。 沖永良部島では、未だ許可を得られていなかったため、マイクさんは、終業後いったんツチノさんの待つ家でふたりの時間を過ごし、軍の門限に合わせ基地に戻る、そして夜は別々に過ごす、そんな生活を余儀なくされた。マイクさんは南部出身の同僚から「ニガー・ラバー」と呼ばれたことがあったそうだ。ニガーとは黒人を蔑視する言葉だが、当時の人種差別の激しさを推し量ることができる。一方でツチノさんは、マイクさんと結婚したことで、日本人の子どもたちから、「パンパン」とはやしたてられたことがあったと言う。パンパンとは、主に戦後に駐軍していた人たちを相手にした売春婦のこと。ツチノさんのような「戦争花嫁」たちは、このような偏見に日々さらされていた。
ようやくふたりが福岡の米国領事館で正式に結婚できたのは1958年のこと。当時アメリカの南部諸州とカリフォルニア州ではまだ、白人と有色人種による結婚を禁止する法律が存在していたため、それらの地域に足を踏み入れた場合、逮捕される可能性があるとする書類に承諾のサインをしなければならなかった。
ツチノさんがアメリカに来たのは、マイクさんの父が亡くなった1960年のことだった。訃報を受け急きょ渡米することになったため、ツチノさんは民間機で、マイクさんは軍用機で、別々にニューヨークの葬儀場へ向かった。日航機でアラスカ、シアトルを経由して、着の身着のままでひとり旅立ったツチノさん。「もう2度と日本へは帰れないだろう、そういう気持ちでやって来たの」。アメリカに持って来ることができたのは、300ドルの現金とスーツケースひとつだけだった。
渡米に当たり、ツチノさんは大きな希望を抱いていた。「アメリカは誰でもチャンスをつかめる国、自分で人生を切り開くんだ、そう言い聞かせていました」。ふたりで生活を始めたオクラホマ州では、「少しの食器と鍋、フライパン。最初に買ったのはそれだけでしたよ。貧乏だけど、自分たちだけの力でやっていく覚悟だった。だから辛いと思ったことなんかないですよ」。とにかく、マイクさんにいい教育を受けてもらうことだけを目標にし、マイクさんには発破をかける日々。それ以外のことはどうでも良かったとツチノさんは語る。「1日に2食しか食べられなくてもいいんです」。マイクさんはツチノさんの倹約家、かかあ天下ぶりに、それまで持っていた「言われたことを何でもする日本人女性」というイメージが完全に覆されたそうだ。マイクさんは、コロンビア大学で学士号、カリフォルニア大学バークレー校で土木工学修士号を取得。軍務に服した後は、連邦航空局に勤務した。
ふたりは何度も引っ越しをしてきた。ワシントンDC、スポケーン、カンザス・シティー、ペンシルベニア州ウィルクスバリ、ニューヨーク州ブレントウッド、サンフランシスコ、アラスカ州のアンカレッジとフェアバンクス、スペインのマドリッド。そして最終的に、ニューヨークと日本の中間にあるシアトルに落ち着く。「アラスカに引っ越す時にこの辺りを通ったんです。当時は庭師さんがたくさんいたので、きれいに剪定された松の木なんかがたくさんあって。『日本みたいで良いところねぇ、いつかはここに落ち着きましょうよ』って、そう決めてたの」