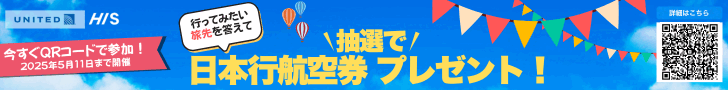子どもとティーンのこころ育て
アメリカで直面しやすい子どもとティーンの「心の問題」を心理カウンセラー(MA, MHP, LMHC)の長野弘子先生(About – Lifeful Counseling)が、最新の学術データや心理療法を紹介しながら解決へと導きます。
うちの子は大丈夫? ADHDとトラウマの関連性と
グレーゾーンの支援方法
子どもの言動に「これってADHDかも?」と悩んだことはありませんか? ADHD(注意欠如・多動症)は遺伝的要因や脳の働きの違いに起因する神経発達症ですが、近年ではトラウマとの関連性も指摘されています。本記事では、ADHDとトラウマに関する最新の研究を紹介するとともに、発達障害「グレーゾーン」の子どもへの具体的な育て方や支援方法をわかりやすく解説します。
ADHDとトラウマの意外なつながり
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の報告によれば、2022年時点でアメリカの3歳から17歳の子どもの約11.4パーセント*(1)がADHDと診断されています。また、離婚や家庭内暴力(DV)、親の死、家族の精神疾患などのトラウマを経験した子どもは、ADHDと診断される可能性が2.5倍高いことがわかっており、トラウマとADHDの間には顕著な関連性が示唆されています。*(2)
トラウマは脳に影響を与え、特に集中力や衝動抑制をつかさどる前頭前野の働きを低下させます。その結果、不注意や多動などADHDに似た行動が現れることがあります。ただし、これらの行動はトラウマによる反応であって、必ずしもADHDそのものではありません。
ADHDとトラウマの違い
1)症状の一貫性:ADHDの場合、家庭でも学校でも一貫して同じ行動特性が見られます。一方、トラウマが原因の場合は家庭や学校など特定の環境やストレス要因によって症状が現れます。
2)原因と背景:ADHDは遺伝的要因が約70パーセントから80パーセントと言われています。一方、トラウマは経験や環境による影響が大きく、幼少期にDVを経験した子どもは、注意力の低下や過敏な反応を示す確率が高いとされています。
グレーゾーンの子どもたちの育て方
ADHDとトラウマの診断基準に完全には該当しないものの、注意力や行動に課題が見られる子どもは「グレーゾーン」と呼ばれます。こうしたの子どもたちは適切な支援を受けられないことが多く、親子ともに不安感や疎外感を感じるケースが少なくありません。しかし、家庭や学校での対応や工夫次第で状況の改善が可能です。以下に具体的な育て方と支援方法を紹介します。
子どもの「困った行動」に日々直面している親にとって、「どうしてうちの子だけ……」と孤独に感じる瞬間は少なくないかもしれません。何度試してもうまくいかず、自分の力不足を感じることもあるでしょう。しかし「完璧な親」である必要はありません。子どもの可能性を信じて一歩ずつ取り組む姿勢が大切です。一人で悩まず、周囲の支援を活用しながら、子どもと一緒に学んでいきましょう。
ADHDとトラウマの意外なつながり
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の報告によれば、2022年時点でアメリカの3歳から17歳の子どもの約11.4パーセント*(1)がADHDと診断されています。また、離婚や家庭内暴力(DV)、親の死、家族の精神疾患などのトラウマを経験した子どもは、ADHDと診断される可能性が2.5倍高いことがわかっており、トラウマとADHDの間には顕著な関連性が示唆されています。*(2)
トラウマは脳に影響を与え、特に集中力や衝動抑制をつかさどる前頭前野の働きを低下させます。その結果、不注意や多動などADHDに似た行動が現れることがあります。ただし、これらの行動はトラウマによる反応であって、必ずしもADHDそのものではありません。
ADHDとトラウマの違い
1)症状の一貫性:ADHDの場合、家庭でも学校でも一貫して同じ行動特性が見られます。一方、トラウマが原因の場合は家庭や学校など特定の環境やストレス要因によって症状が現れます。
2)原因と背景:ADHDは遺伝的要因が約70パーセントから80パーセントと言われています。一方、トラウマは経験や環境による影響が大きく、幼少期にDVを経験した子どもは、注意力の低下や過敏な反応を示す確率が高いとされています。
グレーゾーンの子どもたちの育て方
ADHDとトラウマの診断基準に完全には該当しないものの、注意力や行動に課題が見られる子どもは「グレーゾーン」と呼ばれます。こうしたの子どもたちは適切な支援を受けられないことが多く、親子ともに不安感や疎外感を感じるケースが少なくありません。しかし、家庭や学校での対応や工夫次第で状況の改善が可能です。以下に具体的な育て方と支援方法を紹介します。
1 子どもの特性を理解する
グレーゾーンの子どもには、集中力が続きにくい、指示を忘れがち、感情の起伏が激しいといった特徴があります。まずは、どのような場面で課題が生じるのかを観察し、原因を特定しましょう。親だけでなく、学校の先生や専門家と情報を共有することで、より正確な理解が得られます
2 環境を整える
子どもが集中しやすく安心できる環境を作りましょう。
•スケジュールの視覚化:タスクや予定を視覚的に示すカレンダーやチェックリストを活用する。
•静かな学習環境:音や光などの刺激を減らす工夫をする。
•リラックススペースの設置:落ち着ける場所を用意する。
3 小さな成功体験を積む
小さな目標を設定し、それを達成したときに褒めることで自信を育てます。たとえば「今日は10分間宿題に集中できたね」と具体的な行動を褒めると、子どもは達成感を得やすくなります。
4 コミュニケーションの工夫
子どもにとってわかりやすい指示を心がけましょう。
•短く具体的な言葉で伝える:「片付けて」ではなく「机の上の本を本棚にしまおう」と具体的に伝える。
•感情を言葉にさせる:「怒ってるように見えるけど、何があったか教えて」と声をかけ、気持ちを言葉で表現するよう促すことで、子ども自身が自分の感情を理解をしやすくなります。
5 専門家のサポートを活用する
発達障害グレーゾーンの子どもに特化した支援プログラムやカウンセリングを利用し、具体的なアドバイスや訓練プログラムを受けることも有効です。
グレーゾーンの子どもには、集中力が続きにくい、指示を忘れがち、感情の起伏が激しいといった特徴があります。まずは、どのような場面で課題が生じるのかを観察し、原因を特定しましょう。親だけでなく、学校の先生や専門家と情報を共有することで、より正確な理解が得られます
2 環境を整える
子どもが集中しやすく安心できる環境を作りましょう。
•スケジュールの視覚化:タスクや予定を視覚的に示すカレンダーやチェックリストを活用する。
•静かな学習環境:音や光などの刺激を減らす工夫をする。
•リラックススペースの設置:落ち着ける場所を用意する。
3 小さな成功体験を積む
小さな目標を設定し、それを達成したときに褒めることで自信を育てます。たとえば「今日は10分間宿題に集中できたね」と具体的な行動を褒めると、子どもは達成感を得やすくなります。
4 コミュニケーションの工夫
子どもにとってわかりやすい指示を心がけましょう。
•短く具体的な言葉で伝える:「片付けて」ではなく「机の上の本を本棚にしまおう」と具体的に伝える。
•感情を言葉にさせる:「怒ってるように見えるけど、何があったか教えて」と声をかけ、気持ちを言葉で表現するよう促すことで、子ども自身が自分の感情を理解をしやすくなります。
5 専門家のサポートを活用する
発達障害グレーゾーンの子どもに特化した支援プログラムやカウンセリングを利用し、具体的なアドバイスや訓練プログラムを受けることも有効です。
子どもの「困った行動」に日々直面している親にとって、「どうしてうちの子だけ……」と孤独に感じる瞬間は少なくないかもしれません。何度試してもうまくいかず、自分の力不足を感じることもあるでしょう。しかし「完璧な親」である必要はありません。子どもの可能性を信じて一歩ずつ取り組む姿勢が大切です。一人で悩まず、周囲の支援を活用しながら、子どもと一緒に学んでいきましょう。
参照:
▪️約11.4パーセントがADHDと診断されています(1)
www.mdpi.com/1648-9144/58/2/224
▪️トラウマとADHDの間には顕著な関連性が示唆されています(2)
www.hindawi.com/journals/jdr/2020/8843310
参考記事
(1)Data and Statistics on ADHD
https://www.cdc.gov/adhd/data/index.html?utm_source=chatgpt.com
(2)Study Examines Link Between Toxic Stress and ADHD in Kids
https://spectrumnews1.com/oh/cincinnati/health-and-medicine/2017/02/1/study-examines-link-between-toxic-stress-and-adhd-in-kids?utm_source=chatgpt.com