
写真クレジット:A24
シアトルではシネコンなどで上映中。
母と娘、この世界で葛藤を抱えたことがない母娘の関係なんてあるのだろうか。とりわけ、娘が少女から大人へと脱皮を図る時、独り立ちしたい強い衝動に駆られる娘の変化に、激しく動揺する母も多いだろう。
映画「フランシス・ハ」ですっかりグレタ・ガーウィグのファンになってしまった筆者。彼女の書いた自伝的内容の脚本で初監督作品、しかも主演は23歳の演技派、シアーシャ・ローナンと知り、かなり期待をしていた。この手の期待は裏切られることが多いものだが、本作は期待以上。17歳の娘と母の関係を、ガーウィグらしい独特な切り口で描き出した知的でデリケートな作品で、ひとコマひとコマ、セリフの隅々まで堪能することができた。

カリフォルニア州サクラメントが舞台。主人公はやや頭でっかちのクリスティン、自称レディ・バード(ローナン)だ。カリフォルニアは嫌い、大学は「文化のある」東海岸に行きた いと願っている。ところが、家計を支える看護師の母(ローリー・メトカーフ)は地元のコミュニティー・カレッジで十分と言い張り、ふたりの関係はギクシャク。それでも主人公は親友のジュリー(ビーニー・フェルドスタイン)と楽しいおしゃべりに明け暮れたり、演劇部で出会ったダニー(ルーカス・ヘッジズ)と恋仲になるが思わぬ事態に大泣きしたりなどなど。女子高生の日常に起きる小さな事件が、生き生きとした台詞と共に快活に描かれていく。筆者はそんな主人公を見つめながら、自身のあの頃を鮮やかに思い出していた。

世界が分かったつもりで気負っていたこと、自分は何にでもなれると思っていたこと、母は自分のことなど何も分かっていないと感じていたこと。熱い感情が体から吹き出し、さまざまな発見や思考で脳が破裂しそうになっていたあの頃。そんな娘に対して理解を示す父に反して、母は優しい言葉をかけることもできず、ただ困惑し、娘が進みたい道に立ちは だかる。なんとかそれを突破したい娘。少女が自立した大人に成長して行くために乗り越えねばならない岩礁が母なのだ。こんな痛くて愛しい母親像を描いた作品があっただろうか。観終わってみると、あの母がいたから今の自分がいるというガーウィグの母への愛と返礼の思いが心地よく伝わってきた。
本作は、アカデミー賞の作品賞、主演女優賞、助演女優賞、 監督賞、脚本賞と主要5部門でノミネートされている。
[新作ムービー]

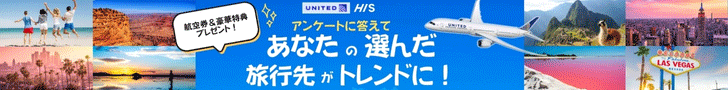











![モルモン信仰の歴史が息づく街 [ソルトレークシティー(アメリカ・ユタ州)]〜旅好きのお気に入り](https://i0.wp.com/soysource.net/wp-content/uploads/2025/03/1_1.jpg?resize=238%2C178&ssl=1)




![街中を歩くだけで心が弾む[ニューヨーク(アメリカ・ニューヨーク州)]〜旅好きのお気に入り](https://i0.wp.com/soysource.net/wp-content/uploads/2025/01/NY2.jpg?resize=238%2C178&ssl=1)


