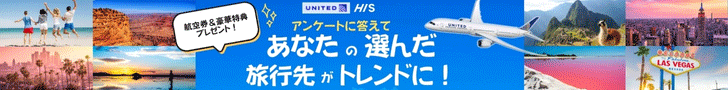毎月数十点が出版され、「教養」「時事」「実用」と幅広い分野を網羅する日本の新書の新刊を通して、日本の最新事情を考察します。
┃ 全共闘世代とは何だったのか

富田 武(ちくま新書)
今年は、1969年1月の「安田講堂事件」から50年という節目の年である。
東大闘争を始めとする大学闘争を総括する『歴史としての東大闘争/ぼくたちが闘ったわけ』(富田 武著、ちくま新書)の著者は、当事者として東大闘争にかかわり、その後大学で歴史を教える立場となった。
当時の「若者」たちはすでに「古稀」前後、今の大学生の祖父母世代となっている。「ぼくたち」はなぜ闘ったのか。歴史家として、また一当事者として、「東大闘争のリアル」を若い世代に伝えたいという思いで本書を執筆したという。
『1971年の悪霊』(堀井憲一郎著、角川新書)の著者は、1958年生まれ。1971年とは、京都の高校で3年生が紛争を起こした年。その直後に入学した著者は、自分たちの高校に機動隊員が突入するという事件を体験した2、3年生との温度差を感じながら高校時代を過ごしていた。自分が左翼思想についていけない、と感じたのはいつ、どんなきっかけだったのか。
反抗する若者たちとその周囲の大人たちが持っていた「社会の気分」、「少し若いの世代の気分」を40年以上経った今、振り返る。
┃ しゃべれないのは悪いこと?

菊池良和(光文社新書)
『吃音の世界』(菊池良和著、光文社新書)は、自身が吃音者として悩み続けてきた体験と、医師としての専門的な立場から吃音についてさまざまな情報を提供する。
吃音者は日常のさまざまな場面で困難や不安を感じ、吃音を隠すために人知れず大変な苦労をしている。以前の著者は、吃音について誰にも相談できず、どもることは悪いこと、人に隠すべきことと思い込み、しゃべる場面を避け「死」も頭をよぎることすらあったそうだ。
著者によれば、吃音者にとって良い聞き手とは、「話している最中は邪魔することなく内容を聞いてくれ、話し終えたときに内容にきちんと反応してくれる人」。当たり前のことのようだが、そうではない人のほうが多いのだという。

『ブロックチェーン/相互不信が実現する新しいセキュリティ』(岡嶋裕史著、ブルーバックス)は、ブロックチェーンという技術の特性、可能性、そして限界について、最小限の基礎知識を理解するための1冊。
ブロックチェーンという用語を一般の人が初めて耳にしたのは、ビットコインの不正アクセスという大スキャンダルがきっかけだろう。その結果、世間的には「ブロックチェーン=ビットコイン=暗号資産(仮想通貨)」という認識が色濃く残っているはずだ、と著者は指摘する。
実際にはブロックチェーンという技術は暗号資産以外の用途への応用も進められている。管理者がいなくても動く仕組みであるブロックチェーンは、「権力からの独立」、「濡れ手に粟」「マネーロンダリング」とセットで語られがちだ。
ブロックチェーンという技術がさまざまな分野に応用され、育っていくことになれば、こうした当初の印象を変え、変化に柔軟に対応していくことが求められてくる、と著者は指摘する。
『昆虫は美味い!』(内山昭一著、新潮新書)の著者は、食材として虫を採り、調理し、食べ続けている「昆虫食の第一人者」だという。食糧難の解決策のひとつとして、家畜に比べて環境への負荷が少ない、持続可能な食料としての可能性が昆虫にあるというのが著者の持論だ。実際、昆虫食については以前では考えられないほど関心・注目が集まってきているという。
昨今、野生鳥獣を食べるジビエ料理もちょっとしたブームになっている。人工化した食への違和感を感じている人が増えているからではないか、と指摘する。
野生鳥獣を食べるのはハードルが高いが、山菜採り、キノコ狩り、潮干狩りのように季節の野生の食材を食べることを楽しむ人は多い。伝統的にイナゴやハチを取って食べる地域もある。
そうした自然との触れ合いとして考えれば、昆虫食もそう特別なものではないのかもしれない。
※2019年1月刊行から(次号につづく)