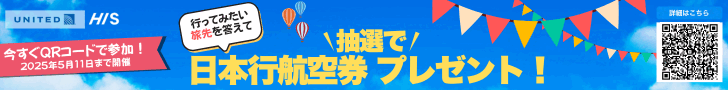教育者から表現者へ
人生を面白く生きる達人
ラ・レーチェ・リーグ 公認リーダー
光岡いずみさん
母乳育児をサポートするラ・レーチェ・リーグの公認リーダーとして32年間活動してきた光岡さん。その一方で、長年にわたり理科教師を務めながら、ピアノやバレエの稽古に邁進し、NPOの運営にも関与するなど、仕事と趣味の垣根を越えて人生を謳歌しています。そんな光岡さんに「面白く生きる」ための人生哲学を語ってもらいました。
取材・文:シュレーゲル京希伊子 写真:本人提供
▲ 毎月1回開催されるラ・レーチェ・リーグの集い。悩みや相談ごとを気楽に話し合い、ポットラックランチを楽しみながら母親同士のつながりを深める。光岡さんが持っているのはカモノハシのぬいぐるみ!
光岡いずみ■1952年東京都生まれ。東京大学理学部修士課程を修了後、都内の高校で4年間、教鞭をとる。81年、夫の仕事の都合で渡米。91年にラ・レーチェ・リーグ公認リーダーの資格を取得し、現在までほぼ毎月集いを開いている。1995年から2019年までシアトル日本語補習学校の理科教師を務め、退職後はJIA主催の成人式USA運営委員に就任するなど、多方面で活躍。
マリー・キュリーに憧れて科学を志す
「リケジョ」という言葉が生まれるはるか前から、光岡さんは正真正銘の理系女子だった。小学校6年生までは国語が大好きで算数は苦手だったが、中学1年生の時、突如、理科に目覚めた。きっかけは学校の実験だった。「水を張ったメスシリンダーに重さ60グラムの石を入れたら、石の重さが40グラムになってるんですよ。え、どうして? 20グラムはどこに行っちゃったの?」当時12歳の光岡さんには、それがとても衝撃的だったという。「質量は変わらないが、重量は変わる」アルキメデスの浮力の原理を目の当たりにした瞬間だった。理科の先生は生徒たちに20グラム減った理由を徹底的に考えさせた。その時光岡さんは、こう気付く。「そうか。世の中って、ボケっと見ていたらダメなんだ」。そこから「物質の根源は何か」を徹底的に調べ尽くし、中2になる頃には高2の理科まで独学で学んでいた。

▲5歳の頃の光岡さん。父親と一緒によく野原で雲を眺めたり、花を摘んだりして、自然への興味が育まれた
「急にリケジョになってしまったんです」と光岡さんは笑いながら当時を振り返る。「文章を書くことが好きだったので、文学者になろうと思っていました。人と関わるのが好きで、中学では生徒会副会長をやるくらいでしたから。元々、文系なんです」。それが、あの実験を境に「マリー・キュリーになりたくなっちゃった」。マリー・キュリーの写真を机の前に貼り、自分も研究者になると決意した。2人の子どもを育てつつ、パートナーとともにラジウムを発見したマリー・キュリーは、女性ながらにノーベル賞を2回も受賞。彼女は、光岡さんにとって目指すべき存在となった。

▲ 生徒会副会長を務め、卒業生代表として答辞を読むなど、リーダーシップを発揮した中学時代
時は1960年代。まだ男女雇用機会均等法が成立する20年以上も前のことだ。女性の職業選択の自由は限られ、賃金格差も激しかったが、当時はそれが普通だった。「女性には参政権もない時代があったのですから」。光岡さんは、先人たちの活動に思いを馳せ、自分も何か行動を起こさなくてはという衝動に突き動かされていた。
光岡さんの母親は教師、いわゆる「職業婦人」だった。母方の祖父も商業高校の教師を務めていた。光岡さんの父親はエンジニアだったが、5人兄弟全員が教師だったことから、教師という職業は身近だった。光岡さんには間違いなく、教師の血が流れている。
こうした時代背景や家庭環境が影響し、光岡さんには「女性解放」に対する強い意識が芽生えていた。折しも、通っていた都立国立高校では上級生が改革を求め、校長室を占拠するストライキが発生。半年も授業が中断され、卒業式も行われなかった。日本中の学生が、「世直し」に熱くなっている時代だった。1年間の浪人生活を経て東京大学に進学した光岡さんは、「このまま出世街道を突き進むのではなく、東京大学に入った人間だからこそ率先して弱者を救わなくては。弱い者も含めた社会づくりこそがいい世の中を生む」との思いが湧き上がり、女性解放運動を標榜するサークルに入った。その頃、出会ったのが、後に夫となる則夫さんだ。

▲東京大学正門前で、女性解放運動のビラを配布。当時はガリ版で印刷していた
 ▲大学院では、水槽に異なる密度の塩水の成層を作り、海水の微細構造の成因を研究していた
▲大学院では、水槽に異なる密度の塩水の成層を作り、海水の微細構造の成因を研究していた一方で、勉学への熱意も消えることはなかった。大学3年で地球物理学科に進むと、流体力学の魅力に取りつかれ、海水データ採取のために観測船に乗りこみ船上生活を送ることもあった。そのまま修士課程に進んだ光岡さんは、順調に海洋物理学者への道を歩んでいたはずだった。
ところが、ある日突然、パニックアタックに襲われる。学会での発表を翌月に控えたことによる極度のストレスが原因だった。入院こそ免れたものの、3カ月間も自宅に引きこもる日々。「自分は社会に必要とされないダメな人間だ」と学会に出られなかった自分を責め続け、家から一歩も出られなくなった。そんな時、すでに社会人となっていた則夫さんが、デートと称してデパートの屋上にあるペット売り場に光岡さんを連れ出す。「そこでハムスターがぐるぐると回り続ける姿を見て、『ああ、がんばって生きてるんだな』と、なぜか救われた気がしました。主人の計らいにはとても感謝しています」。光岡さんの代わりに学会発表を行った研究室の教授にも「あなた中心に地球は回ってないんですよ」と言われたことで、何事にも気が楽になった。
修士号は取得したが、研究者には向いていないことを悟った光岡さんは研究の道を退き、教えることの醍醐味にひかれて高校の理科教師となった。そして間もなく、則夫さんと結婚した。
根底にあるものは、人助けと女性のエンパワーメント

▲長男が生まれたのは、母親の訃報を聞いた直後。長女はまだ2歳で、光岡さんは育児の重圧で大きなストレスを感じていた
1981年、光岡さんは則夫さんの独立を機にロサンゼルスへと渡る。29歳の時だった。全日制の日本人学校ロサンゼルス国際学園で教職に就き、やがて長女を出産。順風満帆に見えたアメリカ生活だったが、またしても精神的な試練に襲われる。肝臓がんで余命半年を告げられていた母親が亡くなったのだ。60歳だった。長男を身ごもり臨月だった光岡さんは葬儀に出席できず、墓前に手を合わせられたのは母の死から5カ月後のこと。2歳と0歳の子どもを抱える身で、母親の壮絶な闘病生活を聞かされ、心の整理がつかず虚脱状態に陥った。それでも「おっぱいが出なくなったらこの世の終わりと思うくらい必死でしたから、母の死の悲しみを棚上げしてしまったんですね。あれは辛かった」。何が光岡さんをそこまで追い詰めたのだろうか。「子育てを完璧にやりたかったのです。母がフルタイムで働いていたため、私たち姉妹は家政婦さんが家に来て面倒を見てくれるという家庭でした。私は、そうではなく、自分は子どもが小さい時は家にいようと思いました。そこに長男が生まれると上の子の赤ちゃん返りが重なり、精神的に参ってしまいました」。
光岡さんは長女を授乳中に「ラ・レーチェ・リーグ」(以下LLL)と出会っている。1956年にシカゴで発祥した、母乳で育てるために必要な情報と励ましを伝え続けるNPO団体で、今では世界中で活動を展開している。LLLから得られるものは知識だけではない。同じ悩みを抱えている母親同士の絆であり、先輩ママからの体験談や助言こそが、LLLの宝だ。「LLLを通じて、単に母乳育児のノウハウだけでなく、精神的なゆとりを得ることができ、子育ての重圧から解放されました」と光岡さんは語る。自分を救ってくれたLLLに恩返しができるならと、公認リーダーへの就任を打診された際、迷わず承諾した。今度は自分が「助ける側」へと回る番だった。
1991年に公認リーダーの資格を取得し、翌年ベルビューに引っ越すと、全米初となる日本語で活動する「ラ・レーチェ・リーグ-イーストサイド・ジャパニーズ」を立ち上げた。現在まで32年間、ほぼ毎月欠かさず集いを開いている。その原動力はどこから湧いてくるのだろうか。「女性を元気にしたいんです」。光岡さんの答えは明確だ。「医者の一言で母乳が出なくなったり、母乳で育てたい女性に正しい情報とサポートが届いていない現実を目の当たりにしてきましたから」。ただし、その役割も時代に合わせて変わりつつある。「今はインターネットで何でも情報が手に入る時代。お母さんたちが求めているのは、知識ではなくて『つながり』です。1カ月に1回会って、元気になる。これが一番大事」。

▲補習学校中学部 理科の授業(果物で電池を作る実験)
理科教師だった光岡さんには、生物の進化について教える際に欠かせないアイテムがある。カモノハシのぬいぐるみだ。実はここに、光岡さんが母乳育児を推奨する理由が隠されている。ほ乳類なのに卵を産むカモノハシは、アヒルのようなクチバシと水かきのついた足を持ちながら、胸にはお乳がにじみ出てくる乳腺もある。「脊椎動物が魚類、両生類、は虫類、鳥類、ほ乳類と進化の過程をたどってきた中で、鳥類からほ乳類になりかかっているのがカモノハシ。つまり、動物は母体の栄養を子どもに与えるように進化してきたのです」と言う。

▲ シアトル日本語補習学校にて。毎回、自分が教材になって授業を行うのが光岡さんのスタイル。実験用の器具や説明用のおもちゃなどをカートに載せて、教室移動していた
自分とは何ぞや-
伝えること、表現することを通して人生最大の謎を解く
伝えること、表現することを通して人生最大の謎を解く
光岡さんは24年間教えてきたシアトル日本語補習学校を2019年に退職して以来、自由の身だ。「私には肩書がないから」と笑うが、携わっている活動を数え出したら片手では足りない。

▲60歳の時、イーストサイド音楽祭「PAFE」の大人部門でショパンのエチュードを演奏し、見事1位に輝く
3歳から18歳までピアノを習っていた光岡さんは再び鍵盤を叩きたくなり、48歳で先生に師事し本格的に再開。ドビュッシーの難曲にも挑戦し、毎年コンテストに出場するまでになった。「自分のためだけではなく、人のためにも弾きなさい」。演奏を通じて自分の喜びを伝えることで、人とつながっていく、という先生の教えに強く共感したという。

▲ ピアノ演奏に必要な体づくりと表現力向上のために始めたバレエ
さらに、「バレエをやるとピアノの表現力が高まる」と言われ、53歳からバレエも習い始める。「身体表現による美とは何か」動き一つ一つに踊り手の哲学が反映されるようなバレエの世界は光岡さんを魅了した。今年の夏にはヨーロッパへ飛び、ハンブルグ・バレエ団の芸術監督ジョン・ノイマイヤー氏による最終公演「マーラー交響曲第3番」を本拠地ドイツで観劇した。本来はオーケストラのために書かれた交響曲をバレエで表現する作品だ。「これを観られたので人生に悔いはありません」。そう言い切れるほどの圧巻の舞台だった。
翻って、光岡さん自身が「きのこ道」と呼ぶ「ピュージェット・サウンド菌類学会(Puget Sound Mycological Society)」の活動もまた、趣味の域を優に超えている。光岡さんは1994年から同学会に所属し、きのこへの愛情は並々ならぬものがある。日本語補習学校でも生徒の間で「光岡先生といえば、きのこ」とまで言われていたという。光岡さんにとって、きのこの魅力とは? 「この世の中は、生産者(光合成をする植物)、消費者(動物)、分解者(菌類)の三者で成り立っています。菌類がいないと世界はゴミと糞尿だらけになってしまうでしょ。有機物を無機物に還す大事な役割を持っているんです」。どこまでも科学者視点だ。探してきたきのこは必ず学名を確認するため、英語と日本語の分厚い専門書にはあちこちに下線が引かれている。毎年10月に開催される同学会主催の「きのこショー」では、各地から集まった会員がそれぞれ採取したきのこを持ち寄って見せ合うそうだ。

▲ 夫の則夫さんと。コロナ禍に結婚40周年を迎えた

▲JIA林間学校にて。生徒が採取した石の成り立ちや種類などを教える光岡さん
光岡さんは、JIA(Japanese In America)Foundation という2014年に立ち上げられたNPOの活動にもかかわってる。毎夏恒例の林間学校では自然教育を担当し、そこで理科の面白さに目覚める生徒も少なくないという。また、来年で6回目を迎える成人式USAは、1月にベルビューのメイデンバウアー・センターで行われる予定だ。光岡さんはその運営委員も務めている。

▲2020年から毎年開催しているJIAの成人式USA。光岡さんは第1回目から運営委員を務めている
多方面で活躍する光岡さんを支える人生哲学とは何だろう。「小説家の開高健が『人生最大の謎とは自分である』と言っていますが、全く同感。自分自身を紐解いていくのを面白がるのが、私の人生哲学です。偶然のように見えても起こったことはすべて必然。まるで、縦横無尽のきのこの菌糸からきのこが出てくるように」。さらにこう続ける。「世の中は複雑系ですが、そのからくりは、意外とシンプルなんです。けれども、今信じられている法則はあくまでも全部仮説。もし500年前に生まれていたら、誰もが太陽が地球の周りを回っているって信じていますよね。それと同じ。世の中の当たり前はどんどん変わって、パラダイムシフトしていくのですよ。人類の叡智の進化ですね」。難解で退屈な理科の話も、光岡さんから学んだらきっと楽しいだろう。育児で悩んでいる時に、光岡さんに励ましてもらったらきっと元気が出るだろう。こうして育つ人の輪は、これからも地域や世代を超えて広がっていくに違いない。

▲ラ・レーチェ・リーグの集いでは、いつも笑いあり涙あり。「わたし一人じゃない、という『悟り』にも似た境地に到達すると、育児は育自になる」と光岡さんは語る