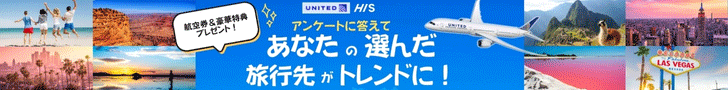人々の健やかで豊かな生活を支える
ソーシャルワーカー 内村 一成さん

長年精神科ソーシャルワーカーとして、日本、カナダ、そしてアメリカで数多くの人々の人生の手助けをしてきた内村一成さん。同時に、子どもの頃からの夢だったアメリカ暮らしを実現させ、広い世界に飛び出すことで自身の幸せもつかみ取ってきたその半生を、じっくりとうかがいました。
取材・文:加藤 瞳 写真:加藤 瞳、本人提供
社会福祉との出合い
「面白いことが好きで、みんなを笑わせることが嬉しかった」。そう語る内村さんの子ども時代。大阪で生まれ育ち、当時まだ東京に進出前のダウンタウンが出演する「4時ですよ〜だ」を観ては、翌日友だちとお笑いの話で盛り上がる。そんなクラスに一人はいるお調子者だった。今も、その明るい笑顔からは朗らかな人柄がうかがえる。
内村さんが社会福祉の道を目指すことになったきっかけは高校生の頃のことだ。「12歳離れた姉に3人子どもがいるんですが、当時小さかった甥っ子が、言葉に詰まることが多く、なかなかうまく話すことができなかったんです。原因がわからない中、姉は児童相談所(以下児相)に相談に行っていました。その話を聞いて、すごくやりがいのある仕事かもしれないと思い、社会福祉学科のある大学を選びました。だから、最初は児相のソーシャルワーカーになりたかったんですよ」。もともとは英語学科を目指していたが、甥っ子を通じて知った児童福祉の世界に心を動かされたという。
その後、大学4年次に実習先となった精神保健クリニックがさらなる変化をもたらした。「精神疾患の方って、特に日本では隠されてしまいがちというか、社会で認知されづらいんです。同居する家族との葛藤や治療、そして回復した先にある就労支援などといった社会復帰のサポートにどのようにクリニックが介入するのか。そのクリニックは実習生でも積極的にアウトリーチ(必要な助けが届いていない人に、支援機関側から出向きアプローチをすること)に同行させてもらえたので、つぶさにその様子を見ることができました。たとえば、引きこもりのクライアントの家を訪問し、どのように働きかけて治療につなげていくのか、先輩の手腕を間近で学びました。精神疾患は寛解(治療をしながら症状を抑えることができている状態)はするけれど、完治(治療を終え、症状が消失した状態)することはないんです。一生病とともに生きながら、どう楽しくポジティブに生きていくかというところをお手伝いできるのが魅力的でした」。卒業後は同クリニックに就職がかない、そこから内村さんの精神科ソーシャルワーカーとしての道が始まった。
シアトルの友人夫妻と独立記念日の一枚
助けを必要とする人のもとへ
精神科ソーシャルワーカーとは? と問うた。統合失調症、そう状態やそううつ、不安神経症、パニック障害といった多様な精神疾患に苦しむ患者が、治療を受けるための橋渡しをし、社会復帰をサポートする役割を担う仕事だ。日本での内村さんの業務も多岐に渡った。「まず、クリニックを訪れた患者さんへのインテイク。睡眠や食欲の有無、服用している薬などに関する問診を行い、そこからドクターにつなげます。そこに辿り着くのが難しい引きこもりの患者さんの場合、家族からの電話などで情報を聞き、一度実際にソーシャルワーカーが訪問します」。内村さんが働き始めた90年代後半は、日本で「引きこもり」が社会問題として重く捉えられ始めた時期。それまで精神疾患患者は、家族の恥になるとタブー視され、親が外に出したがらないことが一般的だったが、この頃から、精神疾患の早期発見・早期治療が求められるようになったそう。大病院では手の届かない場所へ小回りをきかせ、目の届かない所に風穴を開けるように動き回ることができたのが、内村さんの勤めるような地域密着型のクリニックだったという。その中でソーシャルワーカーは重要な役割を担った。「当時うちのクリニックのドクターは初診に40分、以降は15分刻みのスケジュールで患者さんを診ていたので、そこをソーシャルワーカーと、心理テストやカウンセリングを担当する臨床心理士でバックアップするような形でした」。障害年金の申請や医療入院が必要な場合の手配といった事務的な作業から、作業療法やデイケアといったプログラムの準備計画も業務のうち。「精神疾患の治療は、日々のルーティンを作ることが非常に重要になってきます。作業療法は、たとえば封筒作りなど簡単な作業で日々のルーティンを作りながら社会復帰を目指します。また少額でも賃金が支払われるとで自信にもつながります。午前中に作業療法をしたら午後にはデイケア。スポーツやカラオケ、ヨガなんかもありましたね」。こうして着実にキャリアを重ねていた内村さんが海外に飛び出すことになったのはなぜだったのだろうか。
 その人柄に惹かれたというパートナーとは出会った翌年に結婚した
その人柄に惹かれたというパートナーとは出会った翌年に結婚した

2017年、パートナーに生まれ育った場所を見せたいと、連れ立って日本へ一時帰国。母(中央)、内村さんをソーシャルワーカーの道へといざなった姉(正面)、2人の姪とともに

旅行は2人の趣味。毎年11月の旅を楽しみにしている。昨年はトルコ、ギリシャ、クロアチアへ。その前年には南米各国を回った
カナダへの移住
アメリカで暮らしたいという思いは、実は中学生時代にまでさかのぼる。「中学2年生の時、読売新聞主催のホームステイ体験プログラムに両親が応募したんです。LA近郊のパームデールという街で、夏休みの30日間を過ごしました。午前中は公立校で英語の授業を受け、午後は地元のピザ屋でピザを作ったり、ディズニーランドに行ったりといった課外授業があって……。その時、このアメリカという国を実際に体験して、こんな所があるんや、住んでみたいなぁと思ったのが最初でした」。
大学2年次にはカリフォルニア州北部のハンボルト州立大学で1年間の語学留学も果たした。「ハンボルトではESL(English as a Second Language)の取り組みで、週に一度学部授業に聴講生として参加することができました。その時の教授が良い方で、もし大学院に来るなら推薦状を書いてあげるなんて言ってくれて」と、アメリカへの思いはますます強まったのだが……。「やっぱり、アメリカって留学で来るにはすごく学費が高く、その夢はかなえることはできませんでした。でも当時、カナダは年間5000人のワーキングホリデーを受け入れてたんですよね」。
28歳の年、カナダでワーキング・ホリデー・ビザを取り、「生活」をしてみようと一念発起した。こうしてカナダのブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーにやってきたのが2002年のこと。観光業が盛んな同州では、日本語のできる観光ガイドであれば、就労ビザが下りる可能性が高いと聞いた。そこで、思い切って日系旅行会社に就職。8カ月で見事就労ビザを取得した。さらにそこから3年の間になんと移民申請をし、2006年には念願かないカナダ移民となったのだ。その情熱と行動力には舌を巻く。
同年夏にはパスウェイズ・クラブハウスで、メンタルヘルスワーカーとして再スタートを切った。クラブハウスとは、精神疾患を抱えた人々が、医療を介すことなく社会復帰をするためのリハビリテーションモデルの一つ。1940年代にニューヨークで始まったこのモデルは、利用者とスタッフが日常生活のルーティンを共に行い、協調することで生活能力の回復を目指すというものだ。「たとえば当時、私はフード・セクションを担当していました。まずはみんなで材料を買ってきて、作業を分担し調理をする。『トップ・ダウン』ではなく、スタッフとクライアントが一緒に働いて、リカバーしていく、ということをしていました」。
日本の精神科治療は欧米と比較し、かなり遅れを取っているそうだ。「日本には精神病院が多いんです。それはやはり、精神病患者は隠したい、問題がある人は病院に閉じ込めておくという風潮があったからです。それに対し、ヨーロッパやアメリカは地域で治療し、本人の力で早く社会復帰できるように支援します。そこが大きな違いです。その部分で、自分のできる役割を果たしたいという思いでやってきました」。内村さんの口調から、自身の仕事にいかにやりがいを持って向き合ってきたのか、その強い思いが伝わってくる。「回復していく様子が見て取れる時が、本当に嬉しかったです。クラブハウスに来る患者さんは、社会的な恐怖を抱えているけれど、社会の一員でありたいと思って来るわけです。最初はソワソワして30分しかいられなかった人が、1時間過ごせるようになる。それだけでも大きな進歩です。『仕事したいんだけど、何かある?』と聞いてきてくれれば、『アプローチしてくれてありがとう』と心から思います。面接の準備を手伝って就職が決まったりすると、自分が親になったかのように嬉しかったです」。精神科ソーシャルワーカーは、「人の人生に関わることができる仕事」なのだ。

こちらまで明るい気持ちになる笑顔が印象的。あたたかい人柄がストレートに伝わってくる
自分の心にも定期的にメンテナンスを
「カナダで8年働いたんですが、やっぱり人生は一度きりだし、どうせなら本当に住みたい国に住もう! と思い切って、ナフタのTNビザ(北米自由貿易協定に基づき、カナダ国籍を持つ特定の専門職者が米国でビジネス活動を行えるビザ)を取得し、2015年にベルビューの『ヒーロー・ハウス』に来ました」。その後、ベルビュー・クラブハウス、そしてサウンドメンタルヘルスと精神医療一筋でやってきた内村さんだが、昨年大きな転機を迎え、シアトル市の高齢・障害サービス課で、高齢者や身体障害者を対象に長期的な介護のコーディネートを行う部署に転職をした。「ここまで精神科100パーセントだったのが、今では担当する38件のうち、精神科の方は3割にも満たないんです。仕事自体もカウンセリング業務やインテイクではなく、ガラッと変わった。行政なので、税金を使ってのサービス、できることとできないことの線引きが難しいですね」と苦労を語る。行政のサービスに対する利用者の態度は二極化する印象があると言う。「介護サービスを申し込むことができるとこちらがオファーをしても、自分は大丈夫だからと言って受けたがらない人。逆に、なんでもサービスを受けられるなら受けたい、あれもこれも買ってほしい、という人。先日、車椅子を利用しているクライアントで、一人で立ち上がるためにリクライニングチェアを買ってほしいという方がいました。介護ベッドであれば医師の処方箋を書いてもらえれば購入できますが、リクライニングチェアは医療の対象にならないので買えないんですよね。なんでも必要なものを買ってあげられればもちろん良いのですが、税金を無駄遣いするわけにもいかない。こういった問題は最終的に解決しようがないものなので、オフの時でもふとした瞬間に思い出してしまって、そういう時が辛いですね」。
 ワシントン州アネット湖で。雄大な景色を眺めながらのハイキングは、内村さん自身の心の安定を保つための大切な気分転換の
ワシントン州アネット湖で。雄大な景色を眺めながらのハイキングは、内村さん自身の心の安定を保つための大切な気分転換の
一つだ
人の心と体の健康を支える内村さん自身の心が弱ってしまうこともあるだろう。そんな時はどうするのだろうか。「仕事が英語環境なので、日本語の友人と飲みに行ったり、日本語のYouTubeを見たりします。世界各国を回っている日本人ユーチューバーの男性がいるんですが、自分が行ったことがない場所を見て、こんな世界もあるのか、行ってみたいなぁなんて非日常を感じられることがモチベーションにつながります」。内村さん自身も旅行が趣味。毎年必ず一回、大きな旅行を計画し旅に出る。これまで海外はもちろん、アメリカ国内も広く旅をしてきた。「アラスカを除く全ての州を回ってきましたが、今年50歳の記念として、誕生日の週末にアラスカに行き、50州を制覇しました」。プライベートでは、7年前に結婚。憧れ続けた国で、生涯の伴侶とも出会い、幸せをつかんだ。「4年後にパートナーが仕事をリタイアするのに合わせてカナダに戻ろうと思っています。のんびりしたいし、国民健康保険のシステムが整っているので。あとは毎年11月に2、3週間の旅行にいくんですが、今年はポルトガル、スペイン、モロッコを計画しています」。たくさんの人々の人生を支えてきた内村さんは、自身も豊かな生き方の達人なのかもしれない。

ボランティアとして関わる医療福祉関連のボランティア団体、はあとのWA!(www.heartnowa.net)のメンバーと。講演会「心の健康」ではナース・プラクティショナー、メンタルヘルス・インテイク・スペシャリスト、メンタルヘルスワーカーとともに、心の健康を保つアドバイスを行っている。「手助けが必要な時は、一人で悩むのではなく、とにかく連絡してみてほしい」とのこと
image sources
- 01-frontcove1227: © https://soysource.net
- photo1: © https://soysource.net
- photo2: © https://soysource.net
- photo3: © https://soysource.net
- photo4: © https://soysource.net
- photo7: © https://soysource.net
- photo6: © https://soysource.net
- Photo8: © https://soysource.net
- SS-2024-1227_eyecatch: © https://soysource.net