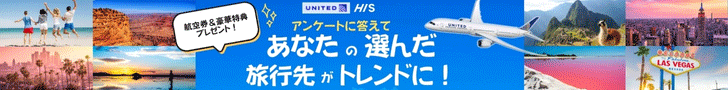箏曲家、宮城道雄。その名を知らなくても、宮城氏の代表作「春の海」は、正月の定番曲として日本人なら誰もが耳にしたことがあるでしょう。今回は、そんな日本の音楽史を語るうえで避けては通れない重要な人物、宮城氏の直弟子である、高村国子さんにインタビュー。
1959年にシアトル宮城会を創設し、以来60年にわたり、箏と三味線(地唄三絃)を教えてきた国子さんの、日本の伝統音楽と共にある人生に迫ります。
取材・文:渡辺菜穂子 写真:渡辺菜穂子、本人提供
宮城先生はとても静かな方でした。
「アメリカでお箏を広めてくださいよ」とおっしゃって。
忘れられません。
「現代邦楽の父」宮城氏との出会い
高村国子さんは、言葉遣いが柔らかく物腰がとても美しい。90歳を過ぎていると聞いていたが、とても見えない。不躾に年齢を尋ねると、「今年で96歳よ」と笑う。若さの秘訣はと問うと、「さあ、のんきだからよね」と微笑みを崩さず、おっとりとした口調で答えてくれた。そして、ひとり言
のように「若い方が来てくださるからね」と付け加えた。
周りの人への感謝がごく自然に口に出る。謙虚で丁寧な極上の品の良さが、そこはかとなくにじみ出ている。自宅兼稽古場で話を聞かせてもらう間、何度も電話がかかってきた。まだまだ、忙しい日々を送っているようだ。
国子さんは1923年に中国で生まれた。帝国主義が終えんに向かう中、争いが絶えない時代だった。両親の母国、日本に戻ったのは10歳の時。仕事のある父親がひとり中国に残り、母親と姉弟と共に東京で育つ。比較的恵まれた暮らしができていたという。箏を始めたのは女学生時代。「その
前もピアノを習ったり、長唄を習ったりしていたんですけれど、あまり合わなくてやめてしまいました。ピアノなんかは姉がとても上手だったから」。女学校で箏を教わった先生に勧められ、東京音楽学校(現・東京藝術大学)に進学した。
宮城道雄氏は当時、邦楽科の教授だった。盲目でありながら箏の名手、そして何より多くの名曲を生み出した大先生として知られていた。後に「現代邦楽の父」と呼ばれるが、その作品に西洋音楽の要素を取り込んで、世界的バイオリニストと共演するなど、その功績は並々ならない。そんな大
先生とのレッスンに、国子さんは常に緊張して臨んでいたそうだ。
しかし、時は第二次世界大戦の真っ最中。東京大空襲が始まった。「宮城先生と一緒に防空壕にも入りました。空襲で家が焼けましたから、私は神奈川県の湯河原に疎開しました。先生も疎開なさって、しばらく東京にはいらっしゃいませんでした」。しかし、戦後も大学卒業後も宮城氏の元
に通う。自身でも生徒を持ち、箏を教えながら10年ほど教えを受け続けた。
宮城氏との思い出でいちばん印象に残っていることはと問うと、しばらく間をおいて、おそらくいろいろな思いを頭にめぐらせながら答えてくれた。「宮城先生はとても静かな方でした。覚えているのは、やはり渡米を決めたことをご挨拶した時です。『アメリカでお箏を広めてくださいよ』とおっしゃって。忘れられません。本当にそんな力、私にはないんだけれどと思いながら」。それが最後の対面だった。宮城氏はその1週間後、突然の事故で亡くなる。結婚式を挙げたばかりだった国子さんは、新婚旅行中に訃報を聞いた。

箏の音を届けるための渡米
国子さんがシアトルにたどり着いたのは、今は亡き夫との縁だという。尺八奏者だった夫は、生まれは日本だが父親の呼び寄せ家族として在米経験があり、アメリカ市民権を取得していた。「アメリカに何十年も住んでいて、日本に帰れない日本人たちがたくさんいる。そんな人たちに、お箏の
音を聴かせてあげて欲しい」。そんな言葉で誘われたそうだ。結婚した翌年、1957年に夫ゆかりのシアトルに移住した。ひと足先に渡米していた夫と、その音楽仲間が、日本からくる箏の先生を待っていてくれた。「準備はできていて、すぐにお稽古が始まりました」。戦時下の日系人強制収容所で三味線を手習った人たちも多く、最高峰の大学を卒業した本格的な先生は大歓迎された。
1959年12月にはシアトル宮城会を結成し、年に2回の定期公演を始め、数々の演奏会を開催するように。1962年のシアトル万国博覧会では、まだ幼かった長女のマーシャさんも箏を披露し、大喝采を受けたそうだ。シアトル総領事の依頼でモンタナまで出向いて1週間ほど出張演奏会をしたこともある。10周年や20周年など節目の大演奏会、ホテルやゴルフ場から頼まれる公演、フルート奏者でもある生徒とのコラボ演奏など、思い出話は尽きない。「小型飛行機でスポケーンまで演奏に行ったこともありました。飛行機が墜落しそうになってね。50年も60年もやっていると、いろんなことがありますね」。国子さんは、箏と日本の伝統音楽をアメリカに広めた功績を認められ、外務大臣や宮城会本部から表彰もされている。

叱るより自分が泣いてしまう
国子さんの人物像を問うと、「とにかく優しいんです」と弟子のひとり、川原律子さん。「もたもたしている生徒さんがいても、先生が何も言わないので、私が後ろから口を出してしまったこともあります。できない生徒さんに『少し家で練習して来られたら』などとは言わない、言えないでしょうね。全然、叱らないんです」
それを聞いた国子さんは、「叱るより先に、こちらが泣いてしまうんです」と目を細める。「何度説明してもわかってもらえないと、情けなくなります。自分の教え方の不甲斐なさに、涙が出るのです」。教えるのは難しい。つい自分で弾いてしまいたくなるのをこらえて、生徒が自分で考え、気付くのを願い見守る、それが国子さんの流儀。「誰でもわかる
時ってありますよね。できなかったことが、ある瞬間ヒュッとできるようになるんです。そんな時は、教えているこちらもうれしくて、『あら、できたじゃない』と一緒に喜びます」これまで、シアトルで教えた弟子は200人前後になる。
全盛期には出張してタコマでも教えていたそうだ。日本人や日系人も多いが、日本文化に引かれてやって来るアメリカ人も少なくない。「バション島からもう30年くらい、通って来ている白人女性のお弟子さんもいます」
文化や習慣が違い、育った環境も違う人に、時代も異なる伝統芸能を教えている。困ったリクエストをされるなど、大変だった生徒もいたと思うのだが。「そうね、いろんな人がいましたけれど、忘れました。大変なことは覚えていないわ」

変わらないこと
1969年に『シアトル・タイムズ』紙の日曜版に掲載された記事を紹介したい。「インターナショナル・ディストリクトから小高い丘を上ったところの住宅街。外から見たらごく普通の家だが、その内部は古典的な日本間になっており、床の間があり、掛け軸がかかり、伝統楽器が並んでいる」。そんな書き出しの記事には、国子さんが弟子と共に着物姿で箏に向かう写真が多く使われ、箏や三味線に関する事細かな説明が続く。「KOTO、1本の木を削って作られる13弦の楽器。床に直接置く場合は、
生徒は床に膝をつけて演奏する。ほとんどの人にとって見慣れない楽器であるが、日本の映画やレコードで、その美しい音を耳にすることはアメリカでも可能だ」
しかし、現在シアトルで生まれ育った人間なら、日本にゆかりのない人でも、伝統楽器「箏」を、1度はどこかで目にしたことがあるだろう。それは国子さんを始め、シアトルにいながら日本文化を大切にしてきて、機会あるごとに公の場で披露してきた多くの人々の功績だ。
残念なことに、記事で描写された日本間は今はない。夫手作りの床の間は漏電で燃えてしまったのだ。全盛期と比べると会員も定期公演の数も減った。しかし、強力な助っ人がいる。長女のマーシャさんも指導を担当しているし、次女のシェリさんは、日本で箏の弦の張り替えを習い、力仕事が難しくなってきた国子さんの代わりに修理を請け負っている。
今も昔も変わらないのは、シアトル宮城会にはウェブサイトもなく、パンフレットもなく、看板も出していないこと。演奏会を見て話しかけてきた人や人づてで聞きつけてきた人、そんな縁で弟子ができる。国子さん率いるシアトル宮城会は、今秋60周年を迎える。久しぶりに本格的な演奏会を開くつもりでいるそうだ。

できなかったことが、
ある瞬間ヒュッとできるようになるんです。
そんな時は、教えているこちらもうれしくて
 高村国子(たかむらくにこ)■1923年、中国生まれ。10歳から日本で暮らし、大学で担当教授だった宮城道雄氏に師事。宮城氏の門人が集まり、1951年に発足した「宮城会」で大師範となる。1957年にシアトルへ渡り、1959年に宮城会のシアトル支部「シアトル宮城会」を創設。シアトル宮城会:☎206-325-9285、seattle.miyagikai@gmail.com
高村国子(たかむらくにこ)■1923年、中国生まれ。10歳から日本で暮らし、大学で担当教授だった宮城道雄氏に師事。宮城氏の門人が集まり、1951年に発足した「宮城会」で大師範となる。1957年にシアトルへ渡り、1959年に宮城会のシアトル支部「シアトル宮城会」を創設。シアトル宮城会:☎206-325-9285、seattle.miyagikai@gmail.com