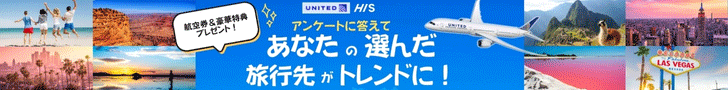東レ・コンポジット マテリアルズ アメリカ社のシニア・テクニカルフェローを最後に、退職を迎えた小田切さんは、約40年にわたり素材業界の最前線を走り続けてきました。通算16年のシアトル駐在生活を終え、日本に帰国する直前に、今だからこそ話せる炭素繊維の開発秘話やボーイング社との提携への道のり、会社人生を振り返っての思い出などを語ってもらいました。
取材・文:シュレーゲル京希伊子 写真:本人提供
化学の無限の可能性を夢見て
15歳になると、小田切さん一家は父親を残して横浜に引っ越した。光化学スモッグがピークに達していた70年代当時、化学は「公害をまき散らす世の中の悪だ」とバッシングの対象だった。小田切さん自身も、自宅付近から富士山が見えたことはなかったという。しかし、「公害をまき散らすのも化学なら、公害を解決するのも化学を担う人の役割なのではないか」。化学の力で、世の中をよくすることはきっとできる。そう考えた小田切さんは、大学で応用化学を専攻した。「化学は手品みたいなものです。帽子の中から鳩が出てくるように、何もないところからモノを作り出すことができるのですから。化学の力は無限です」。修士課程に進むと、人工血管などに用いられる医用高分子材料の開発に取り組む研究室に所属し、高分子学会にも度々参加した。そこでひときわ興味を引いたのが東レの研究者の発表だった。通常、民間企業の発表は機密事項などの制約に縛られる。そんな中、東レの世の中の基礎研究領域の促進に役立つ部分は積極的に公開していくという姿勢は、とても魅力的だった。「この会社なら、自分のやってきた研究が活かせるかもしれない」。それが東レを選んだ理由だった。
炭素繊維の開発から
ボーイング社の認定取得まで
しかし社内では炭素繊維の用途が明確に定まっておらず、社員にアンケートを取ったこともあったという。小田切さんが入社する前の話だ。一時期はギターやマリンバなどの楽器も試作した。「それこそ、『屍の山』でしたよ。作ってはみたものの、値段は高いし、このままでは世の中に通用しない」。しかし社内には、この素材は「いずれ大化けするだろう」との期待があった。
折しも時は70年代。石油危機をきっかけに省エネが叫ばれていた時代だ。軽くて丈夫な炭素繊維に目を付けたのは、アメリカのNASAだった。実はNASAでは、スペースシャトルの部材に炭素繊維複合材(炭素繊維に樹脂などを染み込ませた材料)を採り入れており、その性能を測っているところだった。そこに石油危機が重なり、宇宙産業だけでなく、航空業界でも軽量化が死活問題となっていた。商用機の尾翼やフラップなどにも試験的に採用され、炭素繊維への期待は高まったが、5年以上かけて収集された膨大なデータからわかったことは、「炭素繊維複合材は衝撃に弱い」。金属と違って、炭素繊維複合材は衝撃を受けてもへこまず、外側からはわからない。しかし超音波で検査すると、複合材の内部が損傷し、強度が半分以下に落ちていることもあった。これでは主翼、胴体、尾翼など飛行機の主要な構造部材に使えない。それがNASAの報告書の結論だった。
異なる環境下でも同じ結果が出るのだろうか。たとえば、熱やアルコールにはどれくらい強いのか。塗料や燃料などの化学物質に対してはどうか。疲労させたり、ねじったりしたらどうか。成形できるのか。機体メーカーが現場で百発百中の確率で部材を作れるのか……。実験が成功した後も、途方もない検証プロセスが待っていた。また、研究所だけでなく、技術、製造、工務、知財、法務、営業、購買など、工業製品に仕上げるまでには、ありとあらゆる部署が関わった。まさに総合力の賜物だ。さらに、信頼できる原料メーカーと提携し、安定したサプライチェーンも構築しなければならない。「100万ピースのパズルうちの最初の1ピースを私たちが埋めただけです」。小田切さんの謙虚な発言には、そうした背景がある。
ボーイングの材料認定を受けるには、それだけのプロセスをすべて積み上げて、FAA(アメリカ連邦航空局)のお墨付きをもらわなくてはならない。しかし、航空機材料に求められる基準は果てしなく高い。ビス一本までロット管理されているのが飛行機の世界だ。事故があった際、どのロットの樹脂を使ったのか、その硬化剤は何を使ったのかなど、あらゆる素原料のロット番号までトレースできること。それが事故原因を究明し、再発防止を可能にするためにFAAが求めている基準だった。「こんなことまで資料にするのか」。汎用材料との大きな違いに、小田切さんは面食らった。
ボーイングが80年代初めに材料を募集してから、14年の歳月が経ち、ようやく777型機が初めて試験飛行したのは1994年のことだ。尾翼には東レの製品が使われた。すでに日本に帰国していた小田切さんに代わり、その日、タコマ駐在の社員がエバレットまで初飛行を見に行った。「行ってきました……。飛びました」。電話の向こうの同僚は感無量だった。胸に込み上げてきたうれしさを、小田切さんは今でも忘れない。777型機は翌1995年にユナイテッド航空に納入され、就航した。
故郷岩手を彷彿させるノースウェストで
異業種交流に尽力


▲通算16年の駐在生活で、ノースウェストの大自然を満喫した1992年、東レはワシントン州タコマに製造拠点となる東レ・コンポジットアメリカ社を設立した。小田切さんは2000年から2008年まで、そして2015年から2024年5月までと、2度にわたり同地での駐在を経験している。最初の赴任では、技術部長という立場もあり、もっぱら社内業務に従事したが、2回目の赴任では副社長とシニア・テクニカルフェローの両方を経験して、社外にも交流を広げていった。さらに、2023年にはシアトル日本商工会(春秋会)の会長にも就任したことで、日米協会とイベントを共催したり、沖縄県人会や日系二世退役軍人の集まりに参加したりなど、「日本にいたら絶対に接点がないような人たちと知り合うことができました」。相手が日本人とは限らない。シアトルという土地柄、ロシア、中国、台湾、フィリピン、ベトナムなど、さまざまな民族や人種を身近に感じながら生活した。「彼らともっと交流を深めたかったですね。それだけが心残りです。きっと多くの発見があったはず」。プライベートでも持ち前の社交性で多くの人と友情を育み、スキー、カヤック、ヨット、テニスのほかに、カニ釣りや松茸狩りなど、ノースウェストの大自然を満喫した。



▲収穫品のあさり、わかさぎ、松茸

40年以上もの間、ものづくりに携わってきた小田切さんが、一番伝えたいことは何だろう。「『水を飲むときに、井戸を掘った人のことを忘れてはいけない』。何事にも必ず最初に苦労した人がいます」。水脈があるとわかって掘ったのではない。何遍掘っても空振り。でも、執念と努力の末に掘り当てた人がいる。そういう人の存在は忘れられがちだが、それは違う、と小田切さんは語る。「この話をアメリカ人にもするのですが、英語で”Remember those who dug the well.”と言うと、ちゃんと心に届きます」人の歴史にも、会社の歴史にも、必ず鍵となる出会いがある。「好奇心を持って飛び込んでいくと、芋づる式に人脈がつながっていきます。人との出会いは宝物です」。第二の人生に向けて第一歩を踏み出した小田切さんの挑戦は、まだまだ続く。この先、どんな出会いと発見が待っているのだろうか。小田切さんの興味は尽きない。





▲日米草の根サミットでマシュー・ペリーさんと。マシューさんはペリー提督の5代目の子孫

▲米日カウンシルの仲間と共に。左端が小田切さん
▼親しい仲間に別れの挨拶。小田切さんは、弊誌発行人のトミオ・モリグチとも親交を結んだ