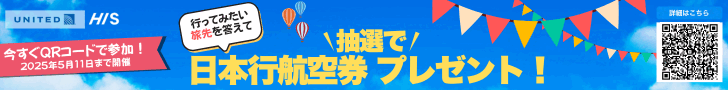┃「死を笑う」のはタブーか

小向敦子(朝日新書)
高齢社会による「多死社会」のこれから、葬儀や墓など死にまつわる事象をこれまで通りに行おうとすると、社会もわれわれもパンクしてしまうのではないか、と指摘するのが『すごい葬式/笑いで死を乗り越える』(小向敦子著、朝日新書)。「死と笑い」という、一見タブーな組み合わせだが、「笑う」ことの作用が、死の恐怖や悲しみに有効なのではないかと訴える。
『住まいで「老活」』(安楽玲子著、岩波新書)では、人生100年時代に、老後の自宅での暮らしを安全で快適にするための住まいの改善ポイントを紹介している。正しい知識があれば、健康寿命を延ばし、「寝たきり」を防ぎ、室内の徘徊など認知症の周辺症状を減らすことも可能であるという。
介護の重症化を防ぐことで、「老後破産」の危険も防げる。著者は、住宅改修アドバイザーとして要介護者の自宅を訪問してきた経験から、当事者、介護者、家族にとっても暮らしやすい住宅改修の基本について紹介している。
重い病気になった時、患者の私たちはどうすれば良いか。『賢い患者』(山口育子著、岩波新書)の
著者は、認定NPO法人「COML(コムル)」の理事長として、患者が主体的に医療に参加するため、
患者や家族からの電話相談に応じるなど、患者の立場から、医学教育に携わる活動を行っている。
COMLが活動を始めた1990年は、「インフォームド・コンセント」の重要性が言われるようになったばかりの頃。それから28年、時代の変化と共に、患者を取り巻く環境は激変している。
以前とは逆に、さまざまな情報が専門知識のない患者にも与えられ、判断を迫られる場面も多い。医者と患者のコミュニケーションの問題など、新たな課題も多く見受けられるという。患者とその家族からの電話相談、自身や親しい人の闘病経験から見聞きしたさまざまなケースを紹介し、医療者に「自分のいのち」を全てお任せするのではなく、主体的に医療に参加する「賢い患者」であることの重要性と難しさについて考えさせられる。

安楽玲子(岩波新書)
┃終着駅から始まる旅

渡辺一夫(中公新書ラクレ)
自他共に認める「世界一の温泉大国」である日本。温泉旅行や心身を癒す効能をテーマにした書籍は数多くあふれている。しかし、日本人はいつ頃から温泉を利用していたのか、今も残る温泉地はいつから始まったのか、など文献史料に基づいて温泉の歴史が書かれている本は意外なほど少ない。
『温泉の日本史/記紀の古湯、武将の隠し湯、温泉番付』(石川理夫著、中公新書)は、そんな温泉の歴史をたどる1冊。『日本書紀』に登場するほど古くから親しまれている道後・有馬・白浜温泉や、「温泉」という言葉が日本で初めて残された『出雲国風土記』、『万葉集』にも登場する温泉地などを紹介する。古来から入浴・温泉文化が普及した背景に、日本の気候風土に加え、入浴や温浴を奨励する仏教の普及があったのではと指摘する。現代の観光資源としての温泉の実態と課題についても触れている。
『ニッポン 終着駅の旅』(谷川一巳著、平凡社新書)は、普通なら行き止まりの、鉄道終着駅から
始まる旅の記録である。終着駅から先には本当に何もなく、その先はどこへも行けず、同じ路線を戻ることになる駅もある。しかし、実はバスやフェリーなどを乗り継ぐと、新たな旅が続けられる場所も多いという。全国津々浦々、さまざまな理由で終着駅になった場所を訪れ、地形の複雑な日本ならではの終着駅の旅情を語る。
旅先で拾ったきれいな石ころを持ち帰る人がよくいる。拾った本人には特別な石かもしれないが、他人から見ればあくまでそれは「石ころ」でしかないことも多々ある。『素敵な石ころの見つけ方』(渡辺一夫著、中公新書ラクレ)の著者は、釣りで出かけた川原で足元の石ころを拾い上げた時から、その魅力と面白さに夢中になり、「理想の石ころ」を探して各地の川原や海岸を旅するようになった。「旅に出たならこの石を探せ」という、地域別の石ころ探しのガイドもある。川原や海岸へ、時間を忘れて石ころ拾いに出かけてみたくなる。
※2018年6月刊行から