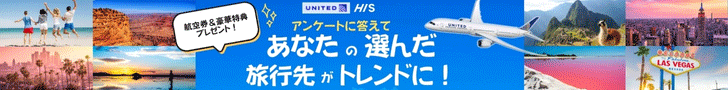┃民主主義の根幹をゆるがす公文書の軽視

日本の「闇」の核心
瀬畑 源著(集英社新書)
『公文書問題/日本の「闇」の核心』(瀬畑 源著、集英社新書)では、情報公開と公文書管理が「いかに大切か」「なぜ重要か」という根本について、歴史的経緯を踏まえて説明していく。公文書を軽んじ、重要事項決定のプロセスを隠蔽し、責任の所在を曖昧にするような事態が常態化することは、国民の知る権利を軽んじ、権力の暴走につながりかねない、と著者は強く警告する。公文書管理の問題は、民主主義の根本を支える重要な問題だということを実感する今、タイムリーな1冊だ。

巨大イベントのデザイン史
暮沢剛巳著(ちくま新書)
『オリンピックと万博/巨大イベントのデザイン史』(暮沢剛巳著、ちくま新書)は、1964年東京オリンピック、1970年大阪万博というふたつの「国家的」巨大イベントを、デザインという観点から振り返る。戦後「デザイン」という概念がまだ定着していなかった日本が、高度成長期を迎えて短期間のうちに、建築、グラフィック・デザイン、プロダクト・デザインなど各分野で高い水準のデザインを実現できた背景を考察している。
2020年東京オリンピックでは、エンブレムとメイン・スタジアムというふたつの大規模な国際コンペが白紙撤回される結果となっている。著者は、このふたつの問題に共通しているのは、コンペで選出されたデザインが国民の広い支持を得られなかったこと、参加資格の制限などから選出の不透明さが感じられたこと、混乱後も責任の所在が曖昧にされたことなどを挙げている。21世紀において「万博」「オリンピック」という巨大イベントの存在意義とは何か、改めて問いただす。
パワハラ、モラハラ、セクハラなど、さまざまな用語でとらえられてきた「職場のいじめ・嫌がらせ」を、深刻な社会問題として考えるべき、と訴えているのが、『職場のハラスメント/なぜ起こり、どう対処すべきか』(大和田敢太著、中公新書)。著者は、ハラスメント規制の先進地域であるEU諸国の法整備についても詳しく、民間団体でのハラスメント相談活動に関わっているという。
「職場のいじめ・嫌がらせ」は、もはや労働者個人レベルのトラブルとして、あるいは個別の企業内での問題として捉えるべきではない、と主張する。職場のいじめ=「ハラスメント」は、企業経営に関わる構造的な問題となっている。社会的問題として「防止・規制」していくものと位置付け、企業の責任体制を明確にし、被害者の救済が可能な制度についても提言する。
┃AI・ロボットに何をどこまで期待するか
人工知能、AIについての話題は尽きない。AIは人間の役に立つのか、会話ができるようになるのか。抽象的な議論に終始しがちなAIについて、最新情報を踏まえて具体的に整理していくのが『誤解だらけの人工知能/ディープラーニングの限界と可能性』(田中 潤/松本健太郎著、光文社新書)。本書では、「2018年現時点」で、AIとは何か、何ができるのか、何ができないのかを簡潔に解説している。AIとは何か、という問いにはさまざまな見解があるが、著者の田中氏は、「2018年現在でのAIとはディープラーニング」であり、「ディープラーニング」を使って何かができるようになれば、それがAIだとシンプルに説明している。
現在「第三次」にある人工知能ブームを支える技術、「ディープラーニング」とは何か、人工知能の基礎的な部分やディープラーニングを始めとする機械学習での限界など、田中氏の専門的な言葉を「翻訳」する役割というもうひとりの著者、松本氏との簡潔で具体的な事例をもとにしたやり取りによって、わかりやすい解説になっている。「人工知能に仕事が奪われるという、根拠のない悲観論ではなく、次の5年、10年を見越して、国や日本企業は、AI関連の研究にもっと投資していくべきではないか」と主張している。

人間とAIの未来
遠藤 薫著(岩波ジュニア新書)
『ロボットが家にやってきたら…/人間とAIの未来』(遠藤 薫著、岩波ジュニア新書)はまさに、「ロボットが私たちの生活に入ってきたらどうなるか」という未来を考えていく1冊。欧米文化の中での「ロボット」と日本文化の中での「ロボット」の受容はどう異なるのか、近代以降の歴史を振り返る。その上で、これからロボットやAIという新しい「他者」との共生はどうあるべきかを、考察していく。著者は、日本のロボット技術は優れていても、これまで「ヒューマノイド型」にこだわり過ぎてきたのではないか、と指摘する。
著者は、もっとも現代的なロボットの姿として、歌声合成ソフトである〈初音ミク〉を挙げている。人型ロボットから一歩離れ、プログラムに従って歌うだけの、身体を持たない〈初音ミク〉をロボットとして見ることで、「ロボット」とは何かを改めて考えさせる。
※2018年2月刊行から
[新書で知る最新日本事情]