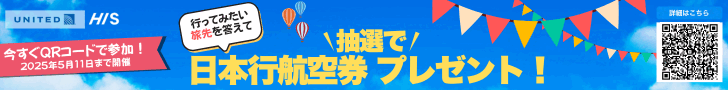北米報知とは
鹿児島出身の隈元 清を発行人として、1902年9月1日創刊。最盛期にはポートランド、ロサンゼルス、サンフランシスコ、スポケーン、バンクーバー、東京に通信員を持ち、約9,000部を日刊発行していた。日米開戦を受けて、当時の発行人だった有馬純雄がFBIに検挙され、シアトル周辺で日系人強制収容が始まろうとしていた1942年3月に廃刊。終戦後、北米報知として再生した。

邦字新聞の誕生
20世紀に入ると、シアトル日本人コミュニティーの発展と共に多くの邦字新聞が誕生した。北米時事は、歯科医だった隅元 清、平出商店創業者の平出倉之助、矢田貝柔二、山本一郎の4名が出資、山田作太郎(鈍牛)を最初の主筆として、1902年9月1日に日刊邦字新聞として創刊した。当時のオフィスは、S. Jackson St.沿いにあった平出商店の階下に置かれた。
『新日本』も同年に創刊。続いて1905年3月1日に『旭新聞』、1910年1月1日に『大北日報』が創刊された。邦字新聞はシアトルに住む日本人にとって、なくてはならない重要な情報源だった。
創業時の主筆たち
新日本に勤務した中島梧街が、ライバル紙の北米時事創刊当時の様子を、回想しながら克明に語っている。 

中島梧街「北米時事と私」(1918年3月29日号)
私が米国に来たのは、1903年7月だった。(中略)その頃シアトルには北米時事と新日本という日刊新聞があって、北米時事は繁栄派を代表し、新日本は廓清派ともいう格であったが、もちろんシアトルを挙げて、黄金万能の時代だったから北米時事の勢力はなかなか強大だった。私は上陸した翌日、東洋貿易会社に山岡音高社長を訪ねて、威勢のいい説教を拝聴させられた後、新日本社に入社した。新日本の黒幕は山岡先生が大御所で、河上主筆始め他に二三の記者がいた。
北米時事は初鹿野梨村が総司令官役、今でこそ俳陣に隠れて活社会に顔を出さない梨村先生も、当時は飛ぶ鳥も落とす勢い、青年文士の随喜するところだった。
忘れてはならぬのは北米時事の隅元社長で、その経営惨憺たる中にあって執着力の強い奮闘振りは目覚ましかった。今は故人となられたが、北米時事の今日あるは隅元社長の寝食を忘れた努力の賜物であると信じる。
(中略)北米時事は突飛的社会廓清には反対だった。むしろある時は急進派の計画を打ちこわしにかかることもあった。よく言えば温和主義、悪く言えば退嬰主義。そこに行く道を異にする二つの日刊新聞の筆戦が開かれた。(中略)私は梨村君の悪口を書くため毎日職工に言いつけて、名誉誹謗の熟語を文選してもらい、取り換え引き換え使用した。梨村君と私の茶話にはよくこのことが話題に上がって、大笑いすることもある。
(中略)私が筆硯を遠ざかって東華州(ワシントン州東部)に赴いた間に、北米時事は一大変化を遂げて昔の下町新聞から解脱し、真面目で立派なデイリーペーパーとなった。私の記憶に残っているのは、藤岡鐵雪(紫朗)君の主筆時代の北米時事である。穏健で真率で同胞の諸問題を真面目に取り扱う誠意は確かに紙面に躍如としていた。今日の同紙面の基礎は、否な形式は藤岡時代に積まれたものだと思う。
今から9年前(1909年)に東華パスコに住んでいた頃、藤岡君に一書を送り、パスコ開発、同胞発展のために応援してもらいたいと頼んだ。すると藤岡君はただちに、快諾の返事を送ってきて私は喜んでパスコ開発の記事を北米時事に連載してもらった。新聞の効果は驚くべきもので、あの砂漠のような荒野に北米時事の記事を見たと言って来訪する同胞は意外に多かった。洗濯屋、雑貨屋が来る。料理屋、中華飯が開店。一時は広告の本尊であるところの私もその応接に忙殺されて底気味が悪く感じたこともあった。新聞紙が地方開発のために貢献した功績は大きかった。(中略)北米時事の悪戦苦闘と同胞の発展のために貢献した努力に対して、満腔の敬意を表したい。
有馬家の活躍
創刊から10年ほどが経った1913年に、北米時事のオーナーシップは隅元から有馬純清へ受け渡される。有馬家は、同紙が日米開戦後の日系人強制収容でその幕を下ろすまで、純清の息子である純義と純雄の代にわたって発行を続けた。社長と主筆を長年務めた純義は、シアトルの北米日本人会会長になるなど日系コミュニティーの中心人物だった。
純義は1941年10月頃に鹿児島で療養していた純清を見舞いに行ったまま開戦でシアトルへ戻れず、弟の純雄が社長を引き継いだが、純雄も真珠湾攻撃と同時にFBIに連行される。純雄は、戦後の北米報知創刊メンバーとして、再開後初の編集長を務めた。
1910年代に北米時事社に勤務した東 良三は、有馬家が北米時事を受け継いだ頃の様子を次のように語っている。
東 良三「三昔前の憶ひ出」 —シアトルと北米時事と僕と— (1938年1月1日号)
僕が初めて北米時事にご縁を持つようになったのは1909年頃、隈元さんが社長の時代で、今、ロサンゼルスにおられる藤岡紫朗氏が主筆であった。(中略)当時、有馬桜岳(純清)先生は明治学院教授の職を辞して渡米され牧師としてタコマに在留されていたが非常に文章家なので、北米時事や大北日報なんかから「タコマ山人」というペンネームで盛んに随筆物を寄せて、僕たち文士仲間の相手となっておられた。(中略)
その後しばらく経って有馬桜岳先生は隈元氏から北米時事を譲り受けて社長兼主筆となった。(中略)現社長の有馬純義氏が父君経営の北米時事の人となったのも確かその頃(1917年頃)であって、ポートランドのカレッジを出たばかりのチャキチャキの青年学徒であった。ちょっとすっぱ抜いておくが、今の有馬さんのマダム(当時福田 環)とのロマンスはポートランド時代に芽生えた。
広がる寄稿者の輪
北米時事を有馬家が受け継いだ後も、創業メンバーや初期の主筆らは、同紙と深く関わっていたようだ。また、元社員の多くが各地から記事を寄稿していた。
1918年1月1日号および1919年1月1日号に当時の北米時事社社員名一覧がある。これを見ると、シアトル本社に二十数名、ロサンゼルス、ニューヨーク、バンクーバーなどに十数名、日本にも数名の社員がいた。有馬純清社長は1919年には一時東京にいたようだ。1930年代には純義が社長を継いでいるので、20年代のどこかで日本へ帰国したのかもしれない。
新日本記者だった中島梧街、また同紙創業者の山岡音高の名前が、社友として並んでいるのは興味深い。中島はこの頃に多くの記事を投稿している。
創業期に主筆を務めた初鹿野梨村が社友として、藤岡紫朗はロサンゼルス駐在として記されている。主筆を退いた後の初鹿野と藤岡について書かれた記事を紹介したい。1918年9月9日号「アラスカ・オーカキャナリーへ赴きたる初鹿野氏は、詩囊を肥して昨日来沙」の記事に対して、初鹿野自身が以下の記事を書いている。
初鹿野梨村「発するに臨んで」(1919年4月19日号)
北米時事が僕の北征を「詩囊を肥やす」云々と書いたので知人が「独り詩囊計りか」とからかうので僕も利かぬ気の、早速一絶をして見せたらハハハと笑って引き下がった。

同号で初鹿野が投稿した「一絶の詩」は筆者の勝手な解釈であるが、「アラスカの荒海の恐怖にうろたえ鴎に笑われ詩嚢を肥やすどころではなかった」という内容ではないかと推測している。からかわれたという知人とは、ひょっとして中島ではなかろうかと想像する。北米時事社創立時にふたりで行った激しい筆戦の延長のようなやり取りの気配を感じる。
1919年10月28日号に「初鹿野氏帰沙」と題し、「アラスカ遠征中なりし初鹿野梨村、昨朝帰沙せる(シアトルに帰る)が、本年は終わり頃になって鮭群寄せ来大漁なりしと語り居たり」とある。初鹿野はこの頃、毎年の鮭漁獲のシーズンにアラスカへ行って、その醍醐味に人生を謳歌していたようだ。
藤岡は、カリフォルニアへ渡って農園家として活躍する一方で、北米時事へ寄稿していたのだろうか。1918年2月5日号によると「羅府(ロサンゼルス)日本人会書記長を辞任後、日加農業組合幹事に就任」とある。藤岡が自身の過去の様子について、次のように語っている。
藤岡紫朗「排日法案」(1939年3月29日号)
当時(1913年頃)私は北米時事記者生活の8年を終え、志を農園方面に立てて、ヤキマへ行った。しかし事業に失敗し1年後にシアトルに帰り恥をさらしていた。それを哀れんだか、古屋、松見両氏がカリフォルニア州行を世話してくれ、私は二つ返事で服装を整え翌日ただちに出発した。
中島梧街についての記事もある。文筆家であると同時に、家庭を大切にする人物であったことがうかがえる一文だ。
「シアトル総まくり」(1918年1月1日号)
北米日本人会の会員様にして口も八丁手も八丁、筆も八丁合わせて二十四丁程の技術を有す。(中略)三男一女の父として模範的家庭を作る。その宰する『ホーム誌』は彼がスイートホームの副産物にして家庭の人としてもまた八丁の手腕あるを証す。